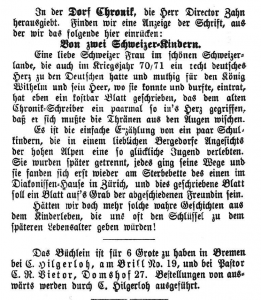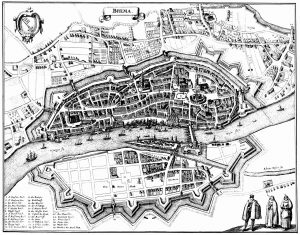> 202 しのぶれば くるしきものを 人しれず 思ふてふこと たれにかたらむ
古今519。題知らず、読み人知らず。
> 203 人しれず おもふこころは 春がすみ たちいでてきみが めにも見えなむ
古今999 「寛平御時歌たてまつりけるついてにたてまつりける」
藤原勝臣
> 204 久かたの あまつそらにも あらなくに 人はよそにぞ おもふべらなる
古今751。題しらず、在原元方。「あらなくに」→「すまなくに」
> 205 たれをかも しるひとにせむ たかさごの まつもむかしの ともならなくに
古今909。題しらず、藤原興風
> 206 おとにのみ きくのしらつゆ 夜はおきて ひるはおもひに けぬべきものを
古今470。題しらず、素性、「けぬべきものを」→「あへずけぬべし」
> 207 わがうへに つゆぞおくなる あまのがは とわたるふねの かいのしづくに
古今863。題しらず、読み人しらず。「かいのしづくに」→「かいのしづくか」
> 208 よし野がは いはなみたかく 行くみづの はやくぞ人を おもひそめてし
古今471。題知らず、貫之。
> 209 世のなかに ふりぬるものは 津のくにの ながらのはしと 我となりけり
古今890。題知らず、読み人知らず。
> 210 足引の 山したみづの うづもれて たぎつこころを せきぞかねつる
古今491。題知らず、読み人知らず。
> 211 ぬきみだす 人こそあるらし したひもの またくもあるか そでのせばきに
古今923。「布引の滝の本にて人人あつまりて歌よみける時によめる」業平。
「ぬきみだす」→「ぬきみだる」、「したひもの」→「しらたまの」、「またくもあるか」→「まなくもちるか」。
古今和歌六帖1711、「またくもあるか」→「まなくもふるか」、または3192「ぬきみだす」→「ぬきとむる」。
業平集59、古今と同じ。
伊勢物語87、「・・・そこなる人にみな滝の歌よます。かの衛府の督まづよむ。わが世をばけふかあすかと待つかひのなみだの滝といづれ高けむ。あるじ次によむ。ぬき乱る人こそあるらし白玉のまなくも散るか袖のせばきに、とよめりければ、かたへの人笑ふことにやありけむ、この歌にめでてやみにけり。」
> 212 ほととぎす なくやさ月の あやめぐさ あやめもしらぬ こひもするかな
古今469。題知らず、読み人知らず。
> 213 たがみそぎ ゆふつけ鳥か から衣 たつたのやまに おりはへてなく
古今995。題知らず、読み人知らず。
> 214 津の国の むろのはやわせ ひてずとも つなをばやはく ものとしるべく
古今和歌六帖2606「きのくにの むろのはやわせ いでずとも しめをばはへよ もるとしるがね」
わかりにくい。「ひでず」は「ひいでず(秀で、穂出の転)」、早稲田に穂が出る前にしめ縄を張ってしまおう、見張っているとわかるように、の意味か。
> 215 なにはがた しほみちくれば あまごろも たみののしまに たづなきわたる
古今913。題知らず、読み人知らず。「しほみちくれば」→「しほみちくらし」。
「雨衣」は「田蓑」にかかる。田蓑の島は淀川河口付近にあった島。
赤人「若の浦に 潮満ち来れば 潟をなみ 葦辺をさして たづ鳴き渡る」の変形か?
> 216 夕されば くものはたてに 物ぞ思ふ あまつそらなる 人をこふとて
古今484。題知らず、読み人知らず。
> 217 あまつ風 雲のかよひぢ ふきとぢよ 乙女のすがた しばしとどめむ
> 218 たちかへり あはれとぞ思ふ よそにても 人にこころを おきつ白波
> 219 こきちらし たきのしら玉 ひろひおきて 世のうきときの なみだにぞかる
> 220 川の瀬に なびくたまもの みがくれて 人にしられぬ こひもするかな
> 221 いくばくも あらじうき身を なぞもかく あまのかるもに おもひみだるる
> 222 すみの江の なみにはあらねど よとともに こころをきみが よせわたるかな
> 223 わたのはら よせくるなみの たちかへり 見まくもほしき たまつしまかな
> 224 あさきせぞ なみはたつらむ よしの河 ふかきこころを 君はしらずや
> 225 わたつうみの かざしにさせる しろたへの なみもてゆへる あはぢしまかな
> 226 こころがへ するものにもが かたこひは くるしきものと 人にしらせむ
> 227 みな人は こころごころに あるものを おしひたすらに ぬるるそでかな
> 228 みちのくの あさかのぬまの はなかつみ かつ見る人を こひやわたらむ
> 229 かつ見れど うとましきかな 月かげの いたらぬさとの あらじと思へば
> 230 我が恋は むなしきとこに みちぬらし おもひやれども ゆくかたもなし
> 231 ふたつなき ものとおもひしを みなそこに やまのはならで いづる月かげ
> 232 なぬかゆく はまのまさごと わが恋と いづれまされり おきつしら波
> 233 われ見ても ひさしくなりぬ すみよしの きしの姫松 いくよへぬらむ
> 234 わたつうみの そこのこころは しらねども 人を見るめは からむとぞ思ふ
> 235 おもひきや ひなのわかれに おとろへて あまのはまゆふ いさりせむとは
> 236 つれなきを いまはこひじと おもへども こころよわくも おつるなみだか
> 237 世の中の うきもつらきも つげなくに まづしるものは なみだなりけり
> 238 わがこひを しのびかねては あしひきの 山たちばなの いろに出でぬべし
> 239 いろなしと 人や見るらむ むかしより ふかきこころに そめてしものを
> 240 おきもせず ねもせで夜を あかしては はるのものとて ながめくらしつ
> 241 なよたけの よのうきうへに 初しもの おきゐてものを おもふころかな
> 242 あはれてふ ことだになくは なにをかも こひのみだれの つかねをにせむ
> 243 世の中は むかしよりやは うかりけむ わが身ひとつの ためになれるか
> 244 わがこひは 人しるらめや しきたへの まくらばかりぞ しらばしるらむ
> 245 たまぼこの みちにはつねに まどはなむ 人をとふとも われとおもはむ
> 246 こひしきに いのちをかふる ものならば しにはやすくぞ あるべかりける
> 247 わびぬれば 身をうきくさの ねをたえて さそふ水あらば いなむとぞ思ふ
> 248 こむ夜にも はやなりぬらむ めのまへに つれなき人を むかしとおもはむ
> 249 しかりとて そむかれなくに 今年あれば まづなげかるる あはれ世の中
> 250 あしがもの さわぐいりえの しらなみの しらずや人を かくこひむとは
> 251 わたつうみの おきつしほあひに うかぶあわの きえぬものから よるかたもなし
> 252 そこひなき ふちやはさわぐ 山川の あさきせにこそ うはなみはたて
> 253 山ざとは ものさびしかる ことこそあれ 世のうきよりは すみよかりけり
『和漢朗詠集』にも出る。古今944 山里は物の憀慄(わびし)き事こそあれ世のうきよりはすみよかりけり。
> 254 木のまより かげのみ見ゆる 月くさの うつし心は そめてしものを
> 255 かりのくる みねのあさ霧 はれずのみ 思ひつきせぬ 世のなかのうさ
> 256 ゆふされば やどにふすぶる かやり火の いつまでわが身 したもえにせむ
> 257 わがこころ なぐさめかねつ さらしなや をばすて山に てる月を見て
> 258 君といへば 見まれまずまれ ふじのねの めづらしげなく もゆる我がこひ
> 259 風ふけば おきつしら波 たつた山 夜半にや君が ひとりゆくらむ
> 260 あやなくて またなきなみの たつた川 わたらでやまむ ものならなくに
> 261 あまの川 雲のみをにて はやければ ひかりとどめず 月ぞながるる
> 262 つなでひく ひびきのなだの なのりその なのりそめても あはでやまめや
> 263 みやこにて ひびききこゆる からことは なみのをすげて かぜぞひきける
> 264 逢ふことの なぎさにしきる なみなれば うらみてのみぞ 立ちかへりける
> 265 あかずして 月のかくるる やま里は あなたおもてぞ こひしかりける
> 266 人しれぬ おもひのみこそ わびしけれ わがなげきをば われのみぞしる
> 267 あかなくに まだきも月の かくるるか 山のはにげて いれずもあらなむ
> 268 いそのかみ ふるともあめに さはらめや あはむといもに いひてしものを
> 269 おもふより いかにせよとか あきかぜに なびくあさぢの いろことになる
> 270 あなこひし いまも見てしか 山がつの かきほにおふる やまとなでしこ
> 271 あれにけり あはれいくよの やどなれや すみけむ人の おとづれもせず
> 272 むらどりの たちにしわが名 今さらに ことなしぶとも しるしあらめや
> 273 あしたづの たてる河辺を ふくかぜに よせてかへらぬ なみかとぞ見る
> 274 人しれず やみなましかば わびつつも なき名ぞとだに いはましものを
> 275 いにしへの 野なかのしみづ ぬるければ もとのこころを しる人ぞくむ
> 276 人しれず ものをおもへば 秋の田の いなばのそよと いふ人もなし
> 277 なにはがた おのがたもとを かりそめの あまとぞわれは なりぬべらなる
> 278 それをだに おもふこととて 我が宿を 見きとないひそ 人のきかくに
> 279 ここにして わがよはへなむ すがはらや ふしみの里の あれまくもをし
> 280 しほみてば いりぬるいその くさなれや 見る日すくなく こふらくおほし