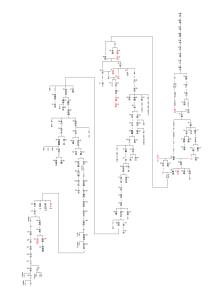正岡子規『墨汁一滴』とは、墨汁一滴分の短い日記という意味だろう。
そういう条件で引き受けた随筆という意味かもしれん。実際かなり短い日もある。
万葉調の優れた歌人として、
源実朝、賀茂真淵、田安宗武、橘曙覧、平賀元義らが挙げられているのだが、
実朝は万葉調と言えなくもないが他の四人とは比べようもない。
実朝の歌はあまりにも特殊なのでとりあえず別格にしたほうがよい。
賀茂真淵には確かに良い歌もある。
あると言えばあるが、せいぜい
> 藤沢や 野沢にごりて 水上の あふりの山に 雲かかるなり
程度である。
田安宗武は良い歌もあるがひどく悪い歌もある。
歌論もあまりぱっとしない。
全体的に大した歌人ではない。吉宗の息子なので過大評価されている。
宗武の歌は後世に非常に悪い影響を与えた。
彼の模倣者は例外なくダメだ。
橘曙覧、悪くはないが、彼も子規によって過大評価されている。
平賀元義は橘曙覧とだいたい同じ。
彼の歌を見ても大したことはない。
つまりは万葉調の叙景歌というだけである。
> うしかひの 子らにくはせと 天地の 神の盛りおける 麦飯の山
悪くはない。しかしすごく良いかというとどうか。
室町・安土桃山の幽玄とか枯淡とかわびさびというものが西洋の自然主義と結びついてできた、
近代特有の和洋折衷な価値観が万葉調と呼ばれているだけに見えるのだ。
実朝の
> 大海の 磯もとどろに 寄する波 われて砕けて さけて散るかも
とか、斎藤茂吉の
> 最上川 逆白波の たつまでに ふぶくゆふべと なりにけるかも
などのようなものを秀歌とする感覚であって、
ハリウッド映画のようなばかばかしさしか感じない。
いや、実朝のはばかばかしすぎて面白いが、茂吉のはただまじめくさってきどっているだけであり、
しかも〆の「なりにけるかも」が陳腐すぎる。
一方実朝の「さけて散るかも」は「かも」で終わる意外性がある。
なんだまた万葉調だったのかと。
平安・鎌倉の武士の歌はもっと情趣があった。
叙景と叙情をうまく結び付けたものだ。
遠景から近景へ、そこから内面描写へ転換するのが見事である。
例えば実朝
> かもめゐる 荒磯の州崎 潮満ちて 隠ろひゆけば まさる我が恋
実朝は叙景歌も叙情歌も、その合わせ技も自在に詠める。
江戸時代の人間は抒情歌が詠めなくなった。
とくに俳句に引っ張られて恋歌というものがまったく詠めなくなった。
だから叙景と叙情を合わせることもできない。
「叙景から叙情への転換」あるいは、
「叙景から叙情への誘導」といってもよいが、
これは和歌の最も得意とする表現だと最近思い始めた。
というかそれが和歌の奥義だと思う。
同じような概念が日本以外の詩にもあるはずだ
(例えば李白「牀前看月光 疑是地上霜 挙頭望山月 低頭思故郷」)。
不思議なもんで、叙情から叙景へはなかなか行きにくい。
和歌というものは、心を種として芽が出て葉となり花が咲くものだとすれば、
外界と心がつながっていなくてはならない。
外から内に入ってきたものがふたたび外へと逆流していくのが歌なのである。
古くは
> 安積山 かげさへ見ゆる 山の井の 浅き心を 我が思はなくに
この古歌もやはり遠景から近景へ、そこから心理描写へと転換している。
> 花さそふ あらしの庭の 雪ならで ふりゆくものは 我が身なりけり
西園寺公経。叙景がイントロとなってふいに自分自身のことを述べている。
それが、唐突ではあるがうまく連結しているのだ。
公経は見ればみるほど優れた歌人である。
業平の
> 世の中に 絶えてさくらの なかりせば 春の心は のどけからまし
紀友則の
> ひさかたの 光のどけき 春の日に しづごころなく 花の散るらむ
などもある意味では同様である。
そこには叙景だけがあるのではない。
子規の
> 藤波の 花をし見れば 奈良のみかど 京のみかどの 昔かなしも
など見るとほんとにがっかりする。
こんなものが秀歌なのか。
> いたつきの 癒ゆる日知らに さ庭べに 秋草花の 種を蒔かしむ
万葉調が鼻につくのがいけない。
「知らに」は「知らず」と同じだが、扱いが難しく使わないのにこしたことはない。
おそらく「知らざるに」という意味に使いたいのだろうが、文法的に少し違う。
「さ庭べ」もこなれない。
「さには」はただの「狭い庭」ではない。
「しむ」も漢文調で歌には似合わないのだが。
万葉調のよろしくないのは古今調以後と比べて文法的に不完全になる危険性が極めて高いところだ。
古今に学べば大けがすることはない。
退屈だが、初心者はまず「春の花」「秋のもみぢ」で練習しなくてはならない。
子規もそうしたはずだが挫折して道を踏み外した。
またこれは「叙情から叙景へ」向かう悪い例だ。
この順番で何がいけないかと言われてうまく答えられないがダメな気がする。
たとえば大伴黒主
> 咲く花に 思ひつくみの あぢきなさ 身にいたつきの 入るも知らずて
子規の歌でも
> いちはつの 花咲きいでて 我目には 今年ばかりの 春行かんとす
こちらは「叙景から叙情へ」向かっている。
セオリー通りの歌ばかり詠むのは味気ないが、
セオリーを外した歌を詠むのはそれなりに理屈がなければならない。
> 雑誌『日本人』に「春」を論じて「我国は旧もと太陰暦を用ゐ正月を以て春の初めと為ししが」云々とあり。語簡かんに過ぎて解しかぬる点もあれど昔は歳の初はじめ即正月元旦を以て春の初となしたりとの意ならん。陰暦時代には便宜上一、二、三の三箇月を以て春とし四、五、六の三箇月を以て夏となし乃至ないし秋冬も同例に三箇月宛を取りしこといふまでもなし。されど陰暦にては一年十二箇月に限らず、十三箇月なる事も多ければその場合には四季の内いづれか四箇月を取らざるべからず。これがために気候と月日と一致せず、去年の正月初と今年の正月初といたく気候の相異を来すに至るを以て陰暦時代にても厳格にいへば歳の初を春の初とはなさず、立春(冬至後約四十五日)を以て春の初と定めたるなり。その証は古くより年内立春などいふ歌の題あり、『古今集』開巻第一に
> 年の内に春は来にけり一年を去年とやいはむ今年とやいはむ
> とあるもこの事なり。この歌の意は歳の初と春の初とは異なり、さればいづれを計算の初となすべきかと疑へる者なればこれを裏面より見ればこの頃にても普通には便宜上歳の初を春の初となしたる事なるべし。
これはつまり「再び歌よみに与ふる書」に
> 先づ古今集といふ書を取りて第一枚を開くと直に「去年こぞとやいはん今年とやいはん」といふ歌が出て来る実に呆れ返つた無趣味の歌に有之候。日本人と外国人との合の子を日本人とや申さん外国人とや申さんとしやれたると同じ事にてしやれにもならぬつまらぬ歌に候。
とあることの焼き直しなのだが、「しゃれにもならぬつまらぬ」話と言いながら、
再びうだうだと考察し直しているのが笑える。
やはり年初と立春の違いが気になるのではないか。
気になるからこそ「古今集」では「年の内に春は来にけり一年を去年とやいはむ今年とやいはむ」
を巻頭に掲げているのだ。
子規も若い頃に「歌よみに与ふる書」を書いたせいで、その重要性に気づいたのだろう。
だが「歌よみに与ふる書」しか見ない人は、「貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候」
としか考えないのだ。