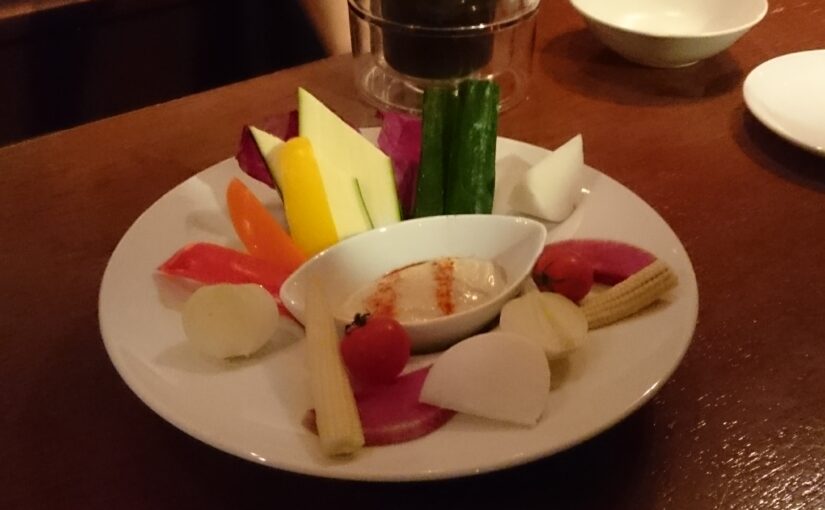筒井康隆の「雨乞い小町」を久しぶりに読んだのだが、
その中で、ずっと気になっていたのだが、
> ことわりや 日の本ならば 照りもせめ さりとてはまた 天が下とは
> ちはやぶる 神も見まさば 立ち騒ぎ 天の戸川の 樋口開けたまへ
の二首があって、「ことわりや」の出来が悪くて「ちはやぶる」の方が良いと言っているところだ。
なぜ筒井康隆は、そう判断したのだろうか。
いろいろ調べてみると面白いのだが、まず、「ちはやぶる」の方は『小町集』『小大君集』に採られており、
小野小町か小大君かはわからぬが、ともかく、平安中期にはもうあった歌なのだ。
ところが「ことわりや」の方がどちらかと言えば有名であって、
初出は江戸初期のいろんな説話集、元はといえば、『雨乞小町』という謡曲(能)の演目の一つだったようだ。
『雨乞小町』は七小町というものの中の一つで、浮世絵の題材には良く採られるが、テキストなど失われて久しいようだ。
弘法大師が京都の神泉苑で雨乞い勝負をしたという伝説があって、
和泉式部もここで同じように勅命で雨乞いをして、そのときに「ことわりや」の歌を詠んだ、
> 日の本の 名に負ふとてや 照らすらむ 降らざらばまた 天が下かは
> ことわりや 日の本ならば 照りもしつ 天が下とは 人もいはずや
などといったバリエーションもあるらしい。
いずれにしても女性が詠んだということになっている。
弘法大師も、竜王という女性に雨乞いをさせたらしい。
雨乞いは女という定説でもあるのだろう。
そういえば、雨女とは言うが、雨男とはあまり言わない。
そうだなあ。どれもできばえは大して違わないように思えるのだが。
いずれにしても、民間の雨乞いの歌だよな、きっと。
加門七海『くぐつ小町』という小説にも「ちはやぶる」の歌が出てくるようだ。こちらは比較的新しい1996年に単行本になった作品。
筒井康隆の『雨乞い小町』の単行本初収録は『ホンキィ・トンク』1973年。
伊勢物語25段。
> むかしをとこありけり。あはじともいはざりける女の、さすがなりけるがもとに、いひやりける
> 秋の野に 笹分けし朝の 袖よりも 逢はで寝る夜ぞ ひぢまさりける
> 色ごのみの女 返し
> 見るめなき わが身をうらと 知らねばや かれなで海人の 足たゆく来る
これらを業平と小町の間でやりとりした歌として解釈している。
筒井康隆が和歌を論じてるのが珍しいので、少し考察してみたいのだが、
これは伊勢物語にも古今集にも採られている有名な歌なので、
筒井康隆が特に和歌に関心を持ったというより、たまたま目について取り上げたにすぎないだろう。
小町の歌は、業平の歌の返歌の形には、まったくなってない。
返歌なら返歌らしく元歌を何か参照するなりしなくちゃならないが、
まったく別々の歌という印象だよな。
ああ、たまたま古今集で隣り合った歌なのか。
筒井康隆の解釈では、これは二人が美男美女の似合いのカップルだと言われて、その気になって詠んでみて、
あまりにも大向こう受けの嫌らしい歌だったので二人とも破って捨てた、
実は二人は恋愛感情よりも友情の方が強くてうんぬん、
という設定。
はて、どうだろうか、そんな解釈ができるだろうか。