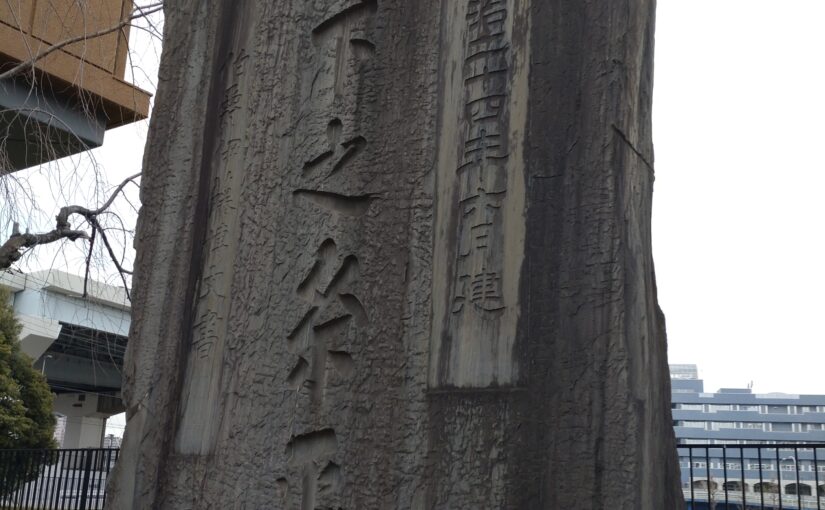ドナルド・キーンという人はまだ存命中の方のようで、88才くらいだろうか。源氏物語か何かを研究して海外に紹介した人、というようなイメージであっているだろうか。「日本人と日本文化」という本で、司馬遼太郎と対談しているのだが、何かずいぶんへんてこなことを書いている。
私は正規に日本史教育を受けた人間ではない。高校では世界史を取った。いわば独学なのだが、それもつい最近、日本外史を精読するようになったから、ついでにいろいろ調べてみているに過ぎない。で、日本史を特に知らなかったころの自分がこの本を読んだら、ふーんなるほどで済ませてしまっていたと思う。なるほど、司馬遼太郎とドナルド・キーンがそういうのならそうなんだろうな、と。しかし、ある程度わかってみて、自分の考えというものが固まってから読んでみるとかなり個性のある、独自の主張、もっというと異様な主張をしているように思えてくるのだ。
特に驚いたのは、足利義政と本居宣長についての評価だ。司馬遼太郎は義政を
法制的には(共和制ローマの)護民官みたいな立場にありながら、まったく政治ということにタッチしなかった
と言っている。また、キーンは
ローマ皇帝のネロが、ローマの燃える炎を見ながら、バイオリンを弾いていたという伝説がありますけれども、これは嘘でしょう。しかし事実として義政公は、花の御所で、いろいろ風流の遊びをし続けていた。そのごく近い所で、多くの人々が死んでいった。
などと言っている。ようするに彼らは、足利将軍をローマ皇帝だか護民官のようなものと比較して、あまりに義政が無為で文弱だった、と言いたいわけだ。しかし私は、もしドナルド・キーンが義政と同じ立場に立たされれば、きっと義政と同じようにやるしかなかっただろうと思う。
足利高氏は逆賊となるよりはと、一族郎党にかつがれて、幕府を作り北朝を立てた。義満の時代に南北朝は解消したが、必ずしも義満に権力が集中したわけではなく、すでに有力守護大名や関東管領らによる合議体に成りつつあった。おそらく南北朝の争乱を通じて将軍家としては、功績のあった諸侯に褒賞として守護職を与え続けるしかなかったのだろう。畠山にしろ細川にしろ山名にしろもとは関東から出てきて足利氏を御輿にして一緒に戦ったわけだが、だんだん足利氏の手に負えなくなった。
ところが足利義教の時、鎌倉公方を滅ぼしたり守護大名の力を押さえたりして、中央集権の強化を図った。義教は足利将軍の中では一番強権的で、帝政ローマの皇帝か共和制の護民官に匹敵したかもしれん。しかし、義教はあんまり調子に乗りすぎたせいで、守護大名の一人の赤松氏に弑されてしまい、赤松氏を討伐した山名氏は赤松氏の領国も合わせてますます強大になった。ここで当時最有力だった細川氏との間で緊張が高まった。
そもそも守護大名らはいくつもの領国を持っていたので、将軍家よりも力を持っていた。山名宗全など赤松氏の領国を合わせて但馬・備後・安芸・伊賀・因幡・伯耆・石見・播磨の八ヶ国の守護職だった。足利氏が独力で細川氏や畠山氏を討伐することなど不可能だし、討伐したらしたで功績のあった大名の領国が増えるだけだ。最悪、赤松氏に殺された義教のように、自分も守護大名に殺されることだってあり得る。そういう状況で義政が大名の家督争いを下手に仲裁しようとしたもんだから、応仁の乱に発展し、日本全土に戦が広まって、長期化してしまった。おそらく、義政にできたことは、荒れ果てた京都において、天皇家や公家らを保護するくらいのことだっただろう。義政は最初はおそらく将軍らしくいろいろな問題を仲裁しようと思ったが、自分にできることがあまりにも少ないので絶望してしまったのだろう。だから早く引退したかったのだが、子供もいないので仕方なく養子を育てることにしたのだが、実子が出来てしまい、正室の日野富子がどうこうということがあって、なかなか将軍職を辞めらなかった。
キーンは、京都に住んで京都大学で研究してたから、京都のことはよく知っていたに違いない。いろんな人からいろいろ義政の話も聞いたのだろうが、義政の極めて一部だけを知って、つまり銀閣寺を建てたとか花の御所で遊び暮らしたとか、そんなことだけをとがめ立てして憤慨しているとしか思えない。
ある意味では気違いだったのでしょうか。
とまで言っている。気違いだとかアスペルガーだとか言ってしまえばもうそれから先は思考停止しかない。
司馬遼太郎はもっとひどい。義政はまったく政治にタッチしなかったのではない。なんとか仲裁し調停しようとはしたのだ。しかし守護大名らは勝手に戦を始めてしまった。軍事力をもたず調整役でしかない将軍が、始まってしまった戦をどうすることができようか。さらに応仁の乱はあまりにも長期的で全国的な争乱だった。おそらくは散発的なものだったのだろう。それで焼け出された民衆を助けるといっても限度があったに違いない。おそらくは、まったくなにもしなかったのではなかろう。やってみたが、焼け石に水だったのだ。それに、民衆を助けるというが、その実態は「足軽」という名のよくわけのわからない民衆たちが、勝手に寺や神社や公家の屋敷などに火を付けて略奪して回った、というのが事実なのではなかろうか。そんな民衆をどうして助けたいと思うだろうか。
なるほど、ドナルド・キーンと言う人が、義政について、よくわからないと。分からないなりに外国人としての視点から指摘をするのはまだ良いが、それについて、きちんと誤りを正す立場にある日本人が、司馬遼太郎のように、
キーンさんは、いわば義政はろくでなしの政治家であるとおっしゃった。まったく言われてみればその通りですが、しかしわれわれは将軍というものに、それほど政治家であることを期待していない。
当時も後世のわれわれも期待してないわけです。
足利将軍家の義政というのは東山文化を生んだたいへん偉大な人物であると、われわれ不覚にも単純に思っていたら、キーンさんはそれを大統領にして、あの「大統領はよくなかった」とおっしゃるからおもしろかった。
などと言ってしまっては、もうどうしようもない。司馬遼太郎の認識では足利義政は銀閣寺はすばらしいくらいでしかなく、そこに外国人から為政者として批判があっても、それにうまく答えられない。そればかりか、無学な北条氏はまじめに政治をやったが、教養人の義政は不真面目だった、要するに学問があるやつは政治にむいてないくらいの、ただの飲み屋の親父が言う程度のことしか言えてない。
思うに北条泰時などは相当なインテリだっただろう。ああいうことはよっぽどきちんと宋学を学んでないとできないはずだ。それに泰時は定家に学んで歌も残している。無学どころではない、きちんと当時の京都の最新の教養を身につけた人だ。始祖の北条時政もずいぶんと利口だった。でなければあんな大それたことはできまい。それがどうして
鎌倉時代の北条三代というのは、無学でしたけれども、一生懸命政治をします。
などということになるのだろうか。司馬はさらに
どうも後世から応仁の乱を考えると、無意味で、どうしようもなくて、ただ騒ぐだけの戦争ですが、
などとも言っているのだが、ようするに、彼にとって秀吉や義経や龍馬のような、わかりやすい英雄とか、わかりやすい決着が不在の戦争、ごちゃごちゃした始まりも終わりもないようなうやむやな内戦のような戦争は無意味でただ騒ぐだけの戦争に見えるということだろう。そういう認識は間違っていると思う。そしてほんとうに問題なのは、日本人の多数が司馬遼太郎程度にしか応仁の乱を認識していないってことだよな。
なるほど。ドナルド・キーンは足利義政について何冊か本を書いているようだな。まあ、だいたい内容の予測はつくが。