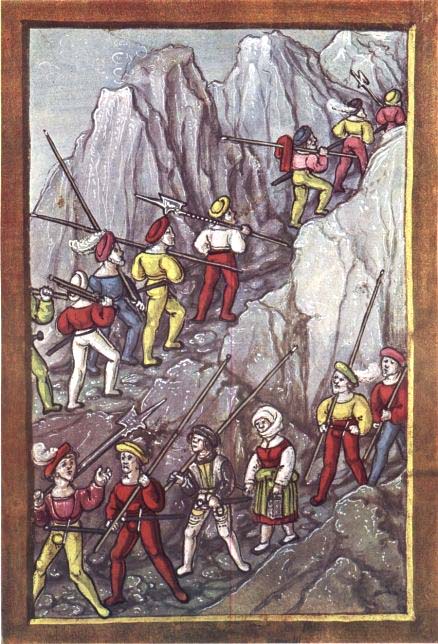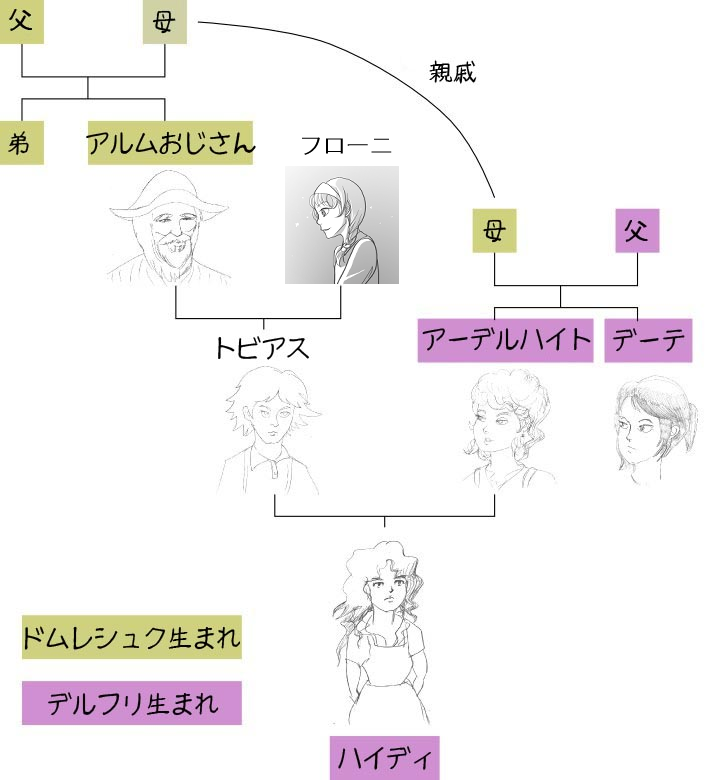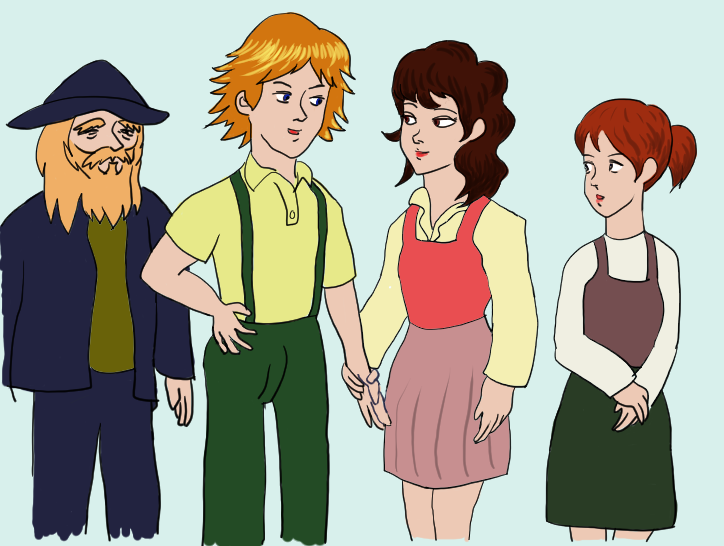ピエモンテ・フランス連合軍にとって、ミラノ奪取までは筋書き通りだった。プロンビエールの密約が漏れたことは、戦況の成り行きに大きな影響はなく、若干シナリオを書き換えるだけでよかった。フランスは中立をよそおい、開戦時にピエモンテ領内にいないことにしたのである。
セージア川の意図的洪水、鉄道の輸送力を駆使した電撃戦、モデナ・トスカーナ方面での陽動策戦、そして何より、フランス・ピエモンテ側の戦意の高さに対して、オーストリア側のへっぴり腰。
イギリス、プロイセンについで産業革命が興り、民主化が進行し、近代工業力を発揮しつつあるピエモンテと、未だ後進のオーストリアでは、国民の、国家の動員力にも差が出てくる。はっきりと目には見えぬが、歴然たる彼我の形勢の違いを、カヴールは肌で感じていた。おっちょこちょいのナポレオン三世をおだてれば、確実にミラノまでは取れる、という周到な準備、絶対の勝算があって、ピエモンテはオーストリアを挑発したのだった。
逆にオーストリアは戦力の逐次投入となってじりじりロンバルディア中原まで後退するだろう。しかし、ポー川下流域におけるオーストリアの守りは堅く、首都ヴィーンからは近く、逆にフランスやピエモンテからは遠い。おそらくここで戦線は膠着状態となって、ピエモンテとフランス、オーストリアの三者間で調整がおこなわれて、休戦協定が結ばれるだろう。その結果、ピエモンテは北イタリアの半ばまでを領有し、モデナ・トスカーナまでは自然と手に入る。教皇領の君主たるローマ教皇の立場は微妙だが、ピエモンテが教皇領をその勢力圏に収めることはできるはず。一方で、ティロルを越えてオーストリアまで攻め入るとか、イタリアをピエモンテ一国で統一しようなどという大それたことを、カヴールが開戦時点で考えていたはずがない。なにしろミラノは北イタリア最大の都市、イタリアの商業・農業・工業の一大拠点である。ここを取れば戦争目的はほぼ達成されたとも言える。フランス人やピエモンテ人が浮かれ騒いだのも理由のないことではない。ギュライ更迭の理由もまた、マジェンタの敗北というよりはミラノを損失したことだった。戦いの勢いとはいえ、実にふがいないことだった。ギュライは戦況が不利と見た時点でミラノ籠城戦に切り替えて、挑発に乗らず、辛抱強く本国からの増援を待つべきだった。ミラノを保っていれば最終的に痛み分け程度に終わったに違いない。
ピエモンテが巨大商圏ミラノを得れば、イタリアの近代化は一気に加速する。つまり、イタリア統一運動も同時に進展せざるを得ない。近代化と民主化と産業革命は三位一体であるからだ。ピエモンテ市民やイタリア統一主義者たちには、もっと勝てるのではないか、いやこの機を利用してもっと勝たねばならない、と欲が出た。しかし、これからがほんとうの正念場だったのである。
オーストリア軍はロンバルディア平原を東へ、半ばまで退却しつつ、皇帝を迎えて反撃の態勢を整えた。こうして近年稀に見る、親征軍どうしの総力戦に発展した。ピエモンテ軍はロンバルディアの士官や兵卒を編入し、オーストリアもハンガリーやヴィーンから兵隊を連れてきて、双方10万人以上の軍勢だ。両軍、否が応でも、戦意は高揚する。フランツ・ヨーゼフ1世、29歳、即位して11年目。叔父フェルディナント1世が革命により退位、その弟のフランツ・カールが帝位を継ぐのを嫌がったのでその長男のフランツ・ヨーゼフが繰り上がって即位した。オーストリアとしては、フランスが皇帝みずから出てきているんだから、こちらも皇帝を出して、全面対決するよかないと思ったんだろうね。欧州随一の名門貴族ハプスブルク・ロートリンゲン家のプリンスとして育ったフランツ・ヨーゼフにしてみれば、降って湧いたような災難だ。
一方のナポレオン3世ボナパルトは51歳。王政時代は帰国を許されず、長年異国の地で亡命生活を強いられた、漂泊の中年貴公子。1830年の革命以来、ボナパルティストたちに担ぎ出され、立候補して議員となり、大統領となり、やがてクーデターで皇帝に即位した。本人は自らの皇帝即位に何も関与してはいない。存在も耐えられない軽さ。いわゆる神輿に過ぎない。取り巻き連中も夢想的帝国主義者やら博愛主義者、ブルジョア社会主義者、芸術家崩れなど。地に足がついた連中ではなかった。かつてたたき上げの軍人だった叔父ナポレオンはイタリア戦線で頭角を表した。ナポレオン3世は、いや彼のプロデューサーであるボナパルティストたちは、このナポレオンの甥も、この戦いにおいてフランス人民が心服する形で勝ち、ボナパルティズムを確固たるものとしたいと考えていた。

カスティリオーネの丘を知っているかね。ソルフェリーノのすぐ近くさ。オーストリアやプロイセンの敵将たちまでが、戦争の芸術と称え、戦争の詩人と称した天才ナポレオンの、中央突破、各個撃滅戦略が、1796年という、かつてのナポレオン戦争のごく初期の段階の、このカスティリオーネの戦いで初めて、萌芽的に現れた、その記念碑的な丘だ。
かの有名なソルフェリーノ戦のとき、俺は前線にはいなかった。何しろ俺たち工兵は東西に長く延びた兵站を維持する輜重隊(しちょうたい)にいて忙しかったのだから。そのうえ皇帝ナポレオンは自分で勝手にどんどんロンバルディア平原を東へ進んでしまう。皇帝は例によって軽はずみな性格だから、1日24時間馬車を乗り継いで移動する。フランスの将軍たちはきりきり舞いで後を追いかける。歩兵は歩いてるヒマもない。重い背嚢と銃剣担いでずっと走りっぱなし。過酷なマラソンだ。本隊とピエモンテ軍が皇帝に追いついたかと思うと、もう2日前に発ちました、と言われる、その繰り返し。
フランス皇帝はプロイセンが介入してくる前に、できるだけ早く決着をつけようと焦ってもいただろう。オーストリアは持久戦に持ち込む腹だろう。
俺たち後方支援部隊などフランス皇帝の眼中にはない。置いてきぼりさ。おかげで命拾いしたよ。同じスイス傭兵でも歩兵や騎兵になった連中は、すわソルフェリーノで戦端が開かれた、ぐずぐずするな、急げとばかりに、順次最前線に追いつき、投入され、ほとんどが戦闘で死んでしまった。
オーストリア皇帝軍は、キエーゼ川を西に、ミンチョ川を東に、ガルダ湖を北に、マントヴァ要塞を南に、フランス軍を迎撃するために南北に長く布陣した。アルプス南麓にはマッジョーレ湖やコモ湖、イゼーオ湖など、多くの湖が並んでいるが、これらはポー川へ流れ落ちる氷河が後退した跡にできた堰止め湖で、ガルダ湖もその中の一つ。イタリア最大の湖である。ミンチョ川はガルダ湖から流れ出してマントヴァを経て南のポー川に注ぐ支流。キエーゼ川もまた、アルプスからオーリオ川に合流しポー川へ流れ込む支流の一つである。キエーゼ川とミンチョ川に挟まれた一帯は、カスティリオーネやソルフェリーノの丘などをのぞけば概ね平坦な田園地帯で、北から南へ、サン・マルチーノ、メードレなどの村が並んでいた。
オーストリア軍は連合軍がまだキエーゼ川の西方、ブレシア辺りにいるものと考え、ガルダ湖南岸まで進出した。一方、連合軍は、オーストリア軍がミンチョ川よりも東にいるものと予測していた。どちらも敵の意表を突こうとして、行軍を速めていたのだ。

ミンチョ川東岸は、マントヴァ、ヴェローナ、ペスキエーラ、レニャーゴという四つの町が、矩形の要塞群を形成していた。オーストリアはナポレオン戦争の頃からこの四つの都市によって囲まれる矩形地帯をロンバルディアの防衛戦にする。だから、フランスはミンチョ川の西岸へ展開して、敵軍に対峙するつもりだった。
しかしオーストリア軍は、ミンチョ川よりずっと西へ進出していたのだ。両軍とも偵察が不徹底で、敵の位置を憶測していたにすぎなかった。
連合軍が先にキエーゼ川を越え、丘の上の村々に至ると、そこはオーストリア軍の宿営地であった。両軍とも作戦不備のまま、不意の遭遇戦となった。まずメードレで、連合軍右翼とオーストリア軍左翼の間に戦端が開かれ、続いてソルフェリーノ、サン・マルチーノなどでも戦闘が発生する。ナポレオン3世の勇猛果敢な陣頭指揮(?)が今回も奏功し、我が連合軍はソルフェリーノを中央突破、 午後から、暴風雨の中の白兵戦となり、前線は大混乱となったが、どちらかと言えば、この悪天候も強気の連合軍に味方した。昼過ぎにはオーストリア軍をカヴリアーナまで押し出す。フランス軍は次々と最前線に到着し、夕刻にヴォルタ・マントヴァーナまで進んだときに、ついにオーストリア軍は総崩れとなって、ミンチョ川の東、ヴィッラフランカまで撤退した。
ソルフェリーノも、マジェンタの戦いと同様、大量殺人の、胸の悪くなるような嫌な戦いだった。予想外の「近間」の戦闘だったから、砲兵どうしが至近距離で大砲を撃ち合い、狙撃兵が歩兵たちを殺戮しまくり、欧州戦史、いや世界戦史にも希な多数の犠牲者が出た。科学の進歩によって、最新鋭の武器は、より「効率的」かつ「残忍」に兵士たちを殺傷することができるようになった(※6)。
戦闘というよりは、無秩序な近代戦力のぶつかりあい。まさに地獄だった。当時はまだ衛生兵というものもなければ民間の赤十字組織も看護婦の派遣もなかった。戦いの規模に比べて、負傷兵の収容所は小さすぎた。兵士は、即死すれば良いが、怪我をすれば、身動きもとれず戦場に放置され、衰弱し、傷口から感染症に罹って、死ぬのを待つだけだったのだ。
ペスキエーラを左に、マントヴァを右に見ながら、ミンチョ河畔にフランス・ピエモンテ軍が会衆したとき、宰相カヴールことカミッロ・ベンゾは珍しく将兵の前に姿を現して、言った。
「諸君。我がイタリア人民の戦いは、まだ半ばに達したに過ぎない。さらなる戦いが、このミンチョ川を越えた先に待っているだろう。
この機会に諸君に紹介したい一人の男がいる。諸君も良く知っていよう。ピエモンテ議会議員にして我が兄、カヴール候グスタヴォだ。いっしょに前線まで来てもらったのだ。
今日、わざわざ私が身内を連れてきて諸君に紹介するのには、わけがある。
兄は我がベンゾ家の当主で、2人の息子がいて、1人はアウグストという名だった。彼はここミンチョ河畔で、ラデツキー軍に敗れて戦死した。1848年、アウグストが20歳の時だ。私は次男坊で、我が領地カヴールを相続することができないから、敢えて妻子を持とうとしなかった。だから私にとって、甥っ子アウグストは本当の自分の子供のようなものだった。諸君らは、今日、やっと兄と私のために、アウグストの仇をとってくれたのだ。どうしても、一言お礼が言いたかったのだ、」と。
俺は、ただむっつりと、カミッロと並び立つ、ベンゾ家の兄グスタヴォの表情を読み取ろうとした。中年貴族らしい、でっぷり肥満したおしゃれなイタリア男。そのときたまたま私の傍らにいた例の中佐殿が、同僚と噂していた、
「もしかしたら、アウグストはカミッロの実子だったかもしれないな。次男に私生児ができたら、その子を領主の跡継ぎの子として育てるってことは、貴族ではありがちな話だよ、」そんな話をね。ほんとうか嘘か知れない、俺の聞き間違いだったかもしれん、或いは彼自身のことを言っていたのかもしれない、彼も貴族で、長男ではなかったから、中佐になったのだろう。今もその話が耳底に残っていてね。
※6 ソルフェリーノの戦いに比べれば、ナポレオンの革命戦争の頃など、まだまだ牧歌的だったといわねばならない。1849年に銃身にライフリングを施したミニエー銃が発明されることによって、世界は一変した。弾は施条によって旋回し、ジャイロのように直進性能が向上、遠く正確に狙撃することができるようになった。歩兵銃だけでなく大砲にもライフリングは応用された。
かつて大砲の弾というのは単なる鋳造の金属球だった。いわゆる砲丸投げの砲丸と同じだ。芯まで鉄の塊だから重い。大砲というものは、その重い鉄の塊を火薬で飛ばし目標にぶつけて加害するものだった。たとえば船や砦に打ち込んで破壊したり、隊列の中へ発射して地上を飛び跳ねながらなぎ倒す目的に使われた。
しかしナポレオン戦争の後で、中空の砲弾の中に火薬を詰めた炸裂弾(グレネード弾、榴弾)が発明される。弾は着弾地点で爆発し、火災を起こす。もしくはパチンコ玉のような鉄球を大量に当たりにまき散らして人を殺傷する。水平射撃で的に直接当てるのでなく、弾道弾によってはるかに遠くの目標も破壊できるようになった。これに加えて砲身の内面に螺旋状の旋条を施した施条砲(ライフル砲)も投入されるようになる。1868年の上野戦争のときに使われたアームストロング砲も施条砲である。
西欧が、産業革命の産物の一つとして近代兵器を生み出す前は、西欧は世界に対して絶対的な軍事的優位に立っていたわけではない。この頃西欧が植民地にしていたのはアメリカやアフリカなどの未開な地域だけである。中国、インド、トルコ、ペルシャなどのアジアの先進諸国と対等に戦う力はまだなかった。
1840年の阿片戦争の時でさえ、イギリス軍と清軍の軍事力にはさほどの差はなかったはずだ。阿片戦争でイギリス軍が勝てたのは、戦艦に大砲を積んでいて、海上を神出鬼没に移動でき、敵の手薄な場所へ艦砲射撃して上陸拠点を確保できたためと、清国政府が沿岸都市部の被害を恐れたためだろう。
しかし、1853年のペリー艦隊の来航、1857年のセポイの反乱、1858年以降のロシアの極東進出、1877年の露土戦争の頃になると西欧の絶対優位性はほぼ確立しており、従って後発のイタリアやドイツなども近代兵器をひっさげて植民地経営に乗り出していったというわけである。
ソルフェリーノ戦はしたがって近代科学戦争の始まり、或いは近代兵器の実験場と言っても良く、西欧における近代兵器の見本市のような役割を果たした。