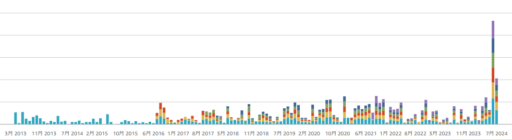『エウメネス』が急に売れ始めたので何かと思い調べてみたら、五年ぶりくらいに『ヒストリエ』の新刊が出たらしい。
『ヒストリエ』と『エウメネス』は主人公がエウメネスというだけで中身はまったく違うものであり、『エウメネス』を書いたとき私はすでに『ヒストリエ』の存在はなんとなく知っていたかと思うが、主人公がエウメネスとは知らなかった。もし知っていたらエウメネスを主人公にすることはなかったと思う。何度もここに書いていることだが、最初は「megas basileus (大王)」というタイトルで、当初エウメネス役の名はニコクラテスという名であった。ニコクラテスはアレクサンドロスの東征とは何の関係もない架空の人物でただひたすらアレクサンドロスを観察する役回りでしかも最初は一人称でもなかった。完全な脇役としてでてくる。良く覚えていないが、ニコクラテスという名はアテナイのアルコン(名親執政官)にいるらしいので、それで適当に見繕ったのだと思う。エウメネスを主人公にしたのは、書記官という立場が私には描きやすかったからだ。一人称にしたのは、そのほうが書きやすかったから。というか、最初の頃は三人称の小説も書いていたのだが、だんだんに一人称のものばかりになっていったのだけど、それはまずもって、一人称のほうが没入感が高いからだ。
エウメネスは一人称だが、本当の主役はアレクサンドロス。読者をエウメネスに感情移入させて、エウメネスの視点からアレクサンドロスを観察させる、という意図でそうなっている。ただしただの地味な書記官に感情移入する読者は少ないと思う。王自身とか剣術使いなどを主人公にしたほうが入り込める読者は多いのだろうが、しょうがないことに私はあまり読者のことを考えて小説を書いていない。自分が面白いように書いている。
だがだんだん長編になってくると一人称のエウメネスのことをいろいろ書くようになって、結局エウメネスが主人公になってしまったのだが。
私が書きたかったのは、大王とはどんな人か、ということだった。だからアレクサンドロスを描いた。アレクサンドロスを観察して分析する主体としてエウメネスという学者がいる。王とは何か、どう考えてどう行動する人かということを考えるというのがこの話の趣旨だ。
トゥキディデスは将軍であると同時に本人がたぐいまれに優れた歴史家であった。クセノフォンもおそろしく優れた戦術家であると同時にトゥキディデスに劣らぬ優れた歴史家であった。しかしながら、当然のことながら、アレクサンドロスは著述家ではない。プトレマイオスはかなり詳しい伝記を残しているらしい(読んだことはないが。おそらくアッリアノスの書いたものの中に断片的に残っているのだろう)。もしアレクサンドロスの側近に優れた著述家がいてくれたら、という私個人の願望がエウメネスというキャラクターを生んだのである。
ちなみにトゥキディデスとクセノフォンについてもわりとしつこく書いた箇所があるから見つけて読んでみてほしい。
小説を書くためにいろいろ調べていくうち、だんだんと興味はセレウコスに移ってきた。セレウコスこそはディアドコイ戦争の最終的な勝利者であり、アレクサンドロスの継承者であり、ローマに滅ぼされるまで続くセレウコス朝を建てたほんものの王者である。
セレウコスは1, 2, 3巻には出てこない。後から1にも書き足したが、4, 5, 6に出てくるキャラである。後半4, 5, 6は私が勝手に書いた創作の要素が多い。かといって前半に少ないというわけではない。4, 5, 6 を書くにあたってさかのぼって1, 2, 3 に伏線を仕込んだりしたからだ。
セレウコスはプトレマイオスの従弟で、ガウガメラから参戦した、オレスティスの若い領主、という設定になっているが、おそらくほぼ史実に沿っていると思う。セレウコスに関する記録や史料はほとんどなく、フィクションで描かなくてはならない部分が多い。
アレクサンドロスには逆に逸話が多すぎる。プルタルコスなんてみんなでまかせの嘘っぱちだ。セレウコスには華やかさはないが優れた治世者だったのは間違いあるまいと思う。セレウコスが再びインド遠征してチャンドラグプタと和約を結んだなんて話はとても面白いのだが、なぜかそういう話を面白がる人は世間には皆無だ。ヨーロッパにもいなかったし当然日本にもいない。
セレウコスの父はアンティオコス。アンティオコスの名はセレウコスが建設したアンティオキアという町の名に残る。セレウコスが作った都セレウキアは今はバグダードと呼ばれている。セレウコスの妻アパマの名をとったアパメアという町も昔はあった。
セレウコスとプトレマイオスが親戚だったことはほぼ間違いない。なぜならセレウコスとかプトレマイオスという名の人物はオレスティスに何人もいて、セレウコスの子がプトレマイオスという名のケースが見られるからである。ギリシャ人は父、祖父、もしくは叔父の名を息子につけることが多かった。しかし自分の名を子につけることはない。
『エウメネス』ではプトレマイオスの父ラゴスと、セレウコスの父アンティオコスは兄弟で、二人ともアロロスのプトレマイオスの子という設定になっている。アロロスのプトレマイオスはペルディッカス三世の摂政で、あった。
これも何度も書いていることだが、このいとこどうしのセレウコスとプトレマイオス朝エジプトの始祖となったプトレマイオスがディアドコイ戦争の真の勝利者である。シリアをセレウコスが治め、エジプトをプトレマイオスが治め、おそらく両者は同盟関係にあった。
ディアドコイ戦争ではアンティゴノスやアンティパトロスやカッサンドロスが注目されることが多いのだが彼らはみなギリシャ残留組であって、アレクサンドロスの後継者でもなんでもない、ただギリシャ本土で彼らの事績が残りやすかったというだけのことだ。西洋史観ではそのあとはすぐにローマ共和国につながっていて、日本人にもその視点しかない。このことがアレクサンドロスの偉業を、西アジアの歴史を非常に見えにくくしている。
ついでに『ヒストリエ』のことを書くと、エウメネスの扱いはまああれでよいとして、アレクサンドロスが予知能力者で、ヘファイスティオンはアレクサンドロスのドッペルゲンガーということになっていて、アレクサンドロスによく似た顔つきの男というのがほかにもでてくるが、これでは歴史を描きようがないと思う。オカルトかファンタジーか。ダンテの『神曲』みたいなものにはなるかもしれないが、いわゆる歴史小説にはなりようがない。そこが『ナポレオン 獅子の時代』とは全然違う。
『ヒストリエ』はいまだにカイロネイアの戦いとかフィリッポス暗殺、アレクサンドロス即位あたりを描いているようだが、そういうマケドニアのローカルな歴史をなぞっている分にはよかろうが、そこから先どうやって世界史につなげていくのか。たぶん作者もまったく見当つかない状態ではなかろうか。
私はやはり、アレクサンドロスとは、ヨーロッパからアジア、インドにいたる、壮大な世界史を描くことに意味があると思っている。ギリシャのちまちました歴史には、興味がないわけじゃないが、インドやペルシャやエジプト、バビュロンやスーサ、ソグドやサマルカンドの話をまんべんなくやらなくてはアレクサンドロスを描く意味がないと思う。
『エウメネス』は最初の1, 2, 3 はほぼ史実通りに書いた。4, 5, 6はかなり脚色した。架空の人物もかなりいるし、史実が残ってないので空想で補わざるを得ないところは作者の特権として好き勝手書いた。しかしながら一応史実を私なりにできるだけ忠実に復元しようと思って書いた。オカルト的要素は(古代史なので皆無ではないが)まったく交えず書いている。そういうものを入れてしまうとなんでもありになってしまい、歴史考察以外の何かになってしまう。
エウメネスがアリストテレスの後継で、アリストテレスはヘルミアスの、ヘルミアスはエウブロスの後継で、ヘルミアスは失脚して、エウブロスの後をメントルが継ぐ。メントルはバルシネと結婚し、バルシネの父アルタバゾスから提督の地位を引き継ぐ。メントルはが死ぬとバルシネはメントルの弟メムノンと再婚する。メムノンが死ぬとアルタバゾスの子ファルナバゾスが継ぐ。ファルナバゾスの後はバルシネの娘と結婚したネアルコスが継ぐ。こうした中で、エウメネスも、アルタバゾスの娘アルトニスと結婚することで、アルタバゾスの閨閥に組み込まれていく、という非常にややこしい話を『エウメネス』ではしているのだが、これも読者が読みたいだろうから書いているのではなく、私が書きたいから書いている。このややこしい話をどう小説に仕立てるのか。ほんとに仕立てられるのか。単なる史実の羅列ではなく面白い読み物に仕立てられるのか。そもそもこんなややこしい話を理解できる読者がいるのか、作者ですら理解できないのに。まあしかしやれるところまでやってみるか。というところが私が今もこの話をリライトし続けている動機といえる。もちろんある程度読まれているからこそリライトしようという意欲もわいてくるのだが。それがたとえ『ヒストリエ』のついでに読まれているとしても。そのうちいつか私の書いたものを単独で面白がる人が現れるかもしれない。
しかし今のところそんな人はほんの数人しかいないことはわかっている。もし私の小説が面白いと思うなら私が書いた『エウメネス』以外の小説も読んでくれるだろうから。しかしそんな人はめったにいない。
エウメネスは「カルディアのエウメネス」と呼ばれるが、実はカルディアの領主だったかもしれない。だとすると、トラキア人かフリュギア人の一領主で、マケドニアがトラキアを征服していく過程で、マケドニアの家臣の一人となり、人質となってペッラに送られ、ミエザで学問を学んで、書記官になった。というのが一番あり得そうな話だ。カルディアはアテナイやスパルタの領地になったこともある。だがそうした場合、本国から執政官が送り込まれるから、その人がカルディアのエウメネスなどと呼ばれるはずがない、と思う。地名を冠するのは領主だからだろう。
ただヘルミアスの例のように、ペルシャでは庶民や奴隷が僭主となることは普通にあったから、エウメネスもそうしたたぐいの庶民であった可能性も全然あるわけである。もしかするとエウメネスは最初からヘルミアスの部下で、カルディアは出身地でもなんでもなく、ヘルミアスにカルディアの統治を任されただけかもしれない。
セレウコスは 358BCくらいに生まれたとされる。アレクサンドロスは356BC生まれなので3才くらい年上ということになる。しかし『エウメネス』ではセレウコスはもっと若く、ガウガメラの戦い(331BC)が初陣でこのとき15才、つまり346BC生まれという設定になっている。セレウコスは 281BC に親戚のプトレマイオス・ケレウノスに暗殺された。また『エウメネス』ではアンティオコスはカイロネイアの戦い(338BC)で死んだことになっているがそういう記録はない。
セレウコスが言われているよりもずっと若いのではないかと私が思ったのは、彼の名が歴史に登場するのがインドに入った後からだ。セレウコスはおそらく身内のプトレマイオス勢の中にいたのだろう。ディアドコイの中では影が薄いなどと言われているのは参戦が遅れた、つまりまだ若すぎたからではないか。
クレイトスやパルメニオンなど、フィリッポス2世の頃からいた旧臣を第1世代、アレクサンドロスと同い年くらい、つまり東征開始時に20才くらいだった連中を第2世代とすると、カッサンドロスやセレウコスは第3世代という具合に、かなり年齢差があるように思われる。
おそらくセレウコスは、人民に慕われるタイプの、やたらと派手な戦争をするのではなく、調整型の君主であった。父や妻の名を冠した都市をいくつも建設したのも同じ理由だろう。家族を大事にし、領民を大事にする。それゆえに自然と人望が集まり、アレクサンドロスの、そしてペルシャの旧領を回収することができたのだろう。そのセレウコスが身内に殺されたのは皮肉だが、アレクサンドロスも、フィリッポス二世も同じように身内に殺されたのだった。