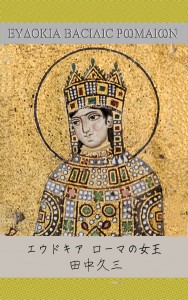[日の神論争](/?p=14161)、[日の神論争2](/?p=14179)の続き。
「日の神論争」と書くのがうざいので、
比較的ましな「日神論争」と書くことにする。
宣長、秋成双方が「日神」という語を用いていることを確認した。
[上田秋成の神霊感](https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp%2Fdspace%2Fbitstream%2F2261%2F25975%2F1%2Frel02405.pdf&ei=19UKU7yBFYnZkAWD-4D4Aw&usg=AFQjCNGwyxSZHlud86bjE6-FVagYzcuGEg&sig2=TtiUTnhRRyH5ujXDAYClFw&bvm=bv.61725948,d.dGI)を読んで思ったのだが、
宣長と秋成の本質的な違いは、
宣長が一神教的な信仰のことを言っているのに対して、
秋成は一神教は間違いであって多神教的態度が正しい、と言っているところだと思う。
世界的には宣長みたいな人のほうが、秋成的な人より多いが、
日本人には秋成みたいに考える人がマジョリティであって、
多くの日本人には宣長の思想は、キリスト教などの一神教に対して感じるような拒絶を覚えるだろう。
たとえば、西洋ではカトリックとプロテスタントが中世に分かれて戦争に発展した。
互いに同じキリスト教徒だという認識はあっても、
一方は他方を異端として容認しない。
宣長も最初のころは秋成のような考え方をしていた。
中国人が中国を世界の中心と考え、儒教を信仰するように、
インド人がインドを世界の中心と考え、仏教(ヒンドゥー教あるいはイスラム教etc)を信仰するように、
日本人は日本が世界の中心であると考え、神道を信じればよいのだ、そう考えていた。
しかしその考え方自体が日本的な多神教の思想であって、
古代ギリシャ・ローマ的多神教と同じ考えであり、
自分には自分の神様がいるが、他の民族には他の神様がいるというので、納得してそれで終わる。
多神教は結局一神教に一方的に譲歩していることになる。
そういう多神教の相対主義は合理的で理知的態度ではあるが、不公平であり不利であって、
そのために日本の宗教は少しずつ仏教や儒教などに浸食され変質していったのであるから、
我々も他の存在を許容しなくて良い、ひたすら自己の神を信仰すればよい。
そうして自らを純粋に保つべきだ。
この考え方は一神教によく似ている。
他の宗教が存在するのは客観的事実である。
自分の宗教以外の規範が存在することをこちらからわざわざ認めてやる必要はない。
一神教はまず、自分以外の神を信仰することを否定する。
知らんぷりして、無視するだけではなく、
しばしば攻撃したり、転向者を罰したり、戦争を仕掛けたりする。
自己以外に宗教が存在しないことが明白なのであれば、そんなことをする必要はない。
そのこと自体が宗教とは相対的であること、つまり多神教を認めていることにならないか。
だが一神教が多神教を認めてしまってはもともこもないから、
自分の宗教だけがほんとうであって、
他の宗教は見せかけの嘘の宗教である、
そういう主張にならざるを得ない。
絶対的な状態から外れているから現状は相対的にみえるだけだ、ということになる。
一神教とは、人間社会を観察すると多神教のようにみえるが、
実は自分の宗教以外は偽物であって、自分だけが正しい、という主張である。
最初はみんな多神教であったが、
どれか一つが自分は一神教であると主張し始めると、
他の宗教も自分こそ一神教であると言わないと、
不利な立場に立たされる。
だから、一神教は次々に伝播していくが、
その発展過程自体が相対的で多様性があって多神教的なのである。
他の宗教との相互作用によって一神教は次第に洗練されていくのだから。
ギリシャ・ローマの多神教が滅んでしまったのは、
一神教の方が優れて好ましい宗教だからではない。
多神教が一神教に一方的に譲歩したせいだ。
一神教のほうが多神教よりも排他的だからだ。
不寛容な宗教が寛容な宗教を長い年月の間に駆逐してしまう。
おそらく宣長が出てかの不寛容な宗教を唱えなければ、
今も日本は仏教や儒教が神道と混淆したままだろう。
日本人でも親鸞や日蓮などは一神教的であるが、
宣長より前の人たちはいずれも仏教や儒教、あるいはキリスト教などの外来の思想を輸入することによって、
その境地に達したのである。
宣長は、仏教や儒教の影響を徹底的に排除し、
それ以前の原始神道を発掘補完することによって、
つまり考古学的古文辞学的手法を用いて、
一切外来の思想によらずに、
一神教的境地に初めて達した日本人である、
国産の一神教を創始した人である、ということがいえよう。
借り物ではない、純国産の宗教が必要だと最初に気づいた人なのだ(実際その需要はあったわけである)。
そうしたときに、秋成のような横やりが出てくると宣長は困る。
宗教とは、世界の宗教を観察して帰結するところでは、不寛容なものである。
神道独りが寛容で物わかりが良くてはならない。
神道は物わかりが悪くならなくてはならない。物わかりが悪いくらいでちょうどいいんだ、
みんなでどんどん理論武装してどんどん物わかりが悪くなろう、
それが宣長の秋成に対する反論なのだ。
日本独自の一神教が創始されるには、
日本において自由な学問が可能になり、
古文辞学などの高度な調査研究手法が確立されるのを待つしかなかった。
それを最初に神道に対して手がけたのが宣長だった。
それは原始神道への回帰をテーマにしてはいるがきわめて近代的・人工的・作為的なアプローチであり
(明治維新が神武天皇への回帰を謳った近代化であったように)、
古代の素朴な宗教とは実はまったく異なるものである。
宣長も、もちろんそのことには気づいていただろう。
そのような一神教的態度そのものが日本古来のものというよりは、
仏教や儒教やキリスト教の影響によるものであり、
その根底には相対主義があり、科学的実証主義があるのである。
宣長もその矛盾には気づいていただろう。
しかし神道をそういうナイーブな状態に放置すれば、
外来宗教や民間信仰によって見る影もなく変質してしまう。
その危機感から彼は一神教的立場をとらざるを得なくなった。
実際世界各地に残っていた原始宗教は、
高度に理論武装されたキリスト教、仏教、イスラム教などによって駆逐されてしまった。
ギリシャ人もローマ人もノルマン人も、キリスト教に飲み込まれて固有の宗教を失ってしまった。
日本にキリスト教やイスラム教が浸透しなかったのは、
すでに仏教によって浸食された後だったからだ。
もし仏教が来る前にキリスト教が伝わっていたら今頃日本はフィリピンのようなキリスト教国になっていただろう。
もし仏教が来る前にイスラム教が来ていたら、マレーシアやインドネシアのようなイスラム教国になっていただろう。
そういう意味では、比較的多神教に寛容な仏教や儒教や道教などが先に日本に伝わり高度に発達していたことは良いことだった(と思うのはすでに相当仏教に脳をやられている証拠かも知れない)。
西洋でも宗教と近代科学は同時並行して発達した。
つまり、宗教を科学的に証明しようとした結果、その副産物として自然科学が発達したのである。
宣長も日本の古き良きものを守ろうとして高度な学問を必要とした。