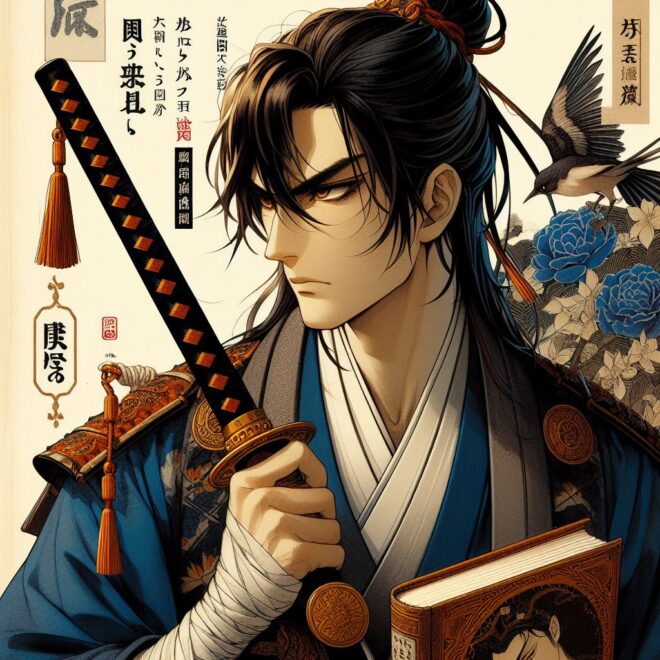60才近くになって、今までいろんな小説を読み映画を見てきておいて、最近は岡本綺堂や野村胡堂や池波正太郎ばかり読んでいる。いや、読むこともあるが、何かの手作業をしながら youtube や audible で聴くことも多い。おそらくこうした捕物小説というものはかつて、シャーロックホームズなどの海外の探偵物を適当に日本風にアレンジしただけの低俗なものだと思われていたのだろう。日本近代文学というものがそうした布教活動をしてきた。
さらに私たちはそれらの捕物小説をテレビドラマ化した、マンネリ化したものをさんざん見させられてきた。それでますます私は、そうした捕物小説というものをバカにして今の年までまともに読まずにきた。
しかしながらふとしたきっかけで、というのは単に私が通院している病院にさいとうたかを版の鬼平犯科帳があって、病院というところは恐ろしく退屈だから読み始めて、それからケーブルテレビのドラマも録画してみたりして、最終的に原作の小説にたどりついたというわけだ。
それでいろいろ見比べてみると、里見浩太朗主演の半七捕物帳は恐ろしくつまらない。原作の雰囲気はほとんどまったく残っておらず、まったく新しい捕物話にしてもらったほうがありがたい。
大川橋蔵主演の銭形平次も最初の1、2話は少し面白いがすぐにつまらなくなってしまう。同じことは暴れん坊将軍にも言える。ぶらり信兵衛道場破りにも同じことがいえる。
鬼平犯科帳も丹波三郎主演のやつは残念ながらあまり面白くない。中村吉右衛門のは少し面白いのもある。しかしいきなり原作には出てくるはずもないくのいちみたいな女が屋根から屋根に飛び移ったりして、原作の雰囲気とかけ離れている。
銭形平次だが、やはり平次が盆栽をいじっているところへ八五郎がてえへんだと言って駆け込んでくるところから始めてほしい。しかしながら平次と八五郎のくだらない無駄話を延々と前振りにすると1話30分だか1時間のドラマの枠にはとうてい入らないのだろう。
今のドラマだと半七や銭形平次の原作の雰囲気に一番近いのは相棒だろうと思う。派手な立ち回りやチャンバラはなくて淡々と謎解きをする。
それでもともとああいうものは低俗な大衆小説を低俗なドラマに仕立てたものだとみなされてきたのだと思うが、今読み直してみると、少なくとも原作の小説は、今となっては到底書けないような江戸時代の情緒や雰囲気が描かれていて、昔はこういうものはいくらでもあったのかもしれないが、現代では非常に貴重な読み物だということがわかる。
明治や戦後、江戸時代のものはなんでも懐古主義で無価値なものとみなされていた時代には極めて軽く見られていたが、今となっては非常に貴重なものだ。
もし江戸時代の風俗を調べようと思うと、当時の黄表紙や読み本なんかを見なくてはならずとんでもないてまひまがかかる。それよりかは岡本綺堂の半七などを読むのがずっと手っ取り早い。
刑事コロンボは69話で打ち切りになったのだが、最初はすごく緻密で面白かったのにだんだんつまらなくなった。終わりの頃のコロンボは相棒よりもつまらない。マンネリがいかに恐ろしいかということの典型的な実例だ。
しかし日本のテレビドラマだとそれでも打ち切りにはならず、単に俳優をすげ替えただけのさらにつまらなくなった続編を作り続ける。しかしそうしたものにもなんらかの需要もしくはよんどころない事情があってテレビ放映されるのだろうが、おかげで私などはテレビドラマなぞは見る価値の無いものだという固定観念(固定諦念というべきか)が完全にできあがってしまった。
ドラゴンボールもマンネリになって打ち切られたのだろうし、その反省から、ワンピースは最初からマンネリ化することを想定したうえで、プロットが作られ作者が選ばれ、マンネリ化した状態を維持する前提で話を引き延ばす戦略に出ているのだと思う。弁当をコンビニで並べるように保管や流通を工夫するのではなく、最初からコンビニに並べるための弁当作りをするようなものだ。
はっきりいって今の少年ジャンプは私にはまったくおもしろくないのだが、あれだけ売れているということは需要があるのだろう。つまり笑点やさざえさんのようにマンネリ化した定常状態というものにある一定の需要があるからこそ作られている。はっきりいってまったく付き合いたくない世界だ。せめて007シリーズくらい努力してくれれば私も見続けるかもしれないが。
ついでだが、私はスティーブンソンの『宝島』はよく出来た海賊物だと思っている。当時のカリブ海あたりの風俗がそのまま記されているように感じる。ワンピースのようなまがいものが日本人に受けるのは仕方ないかと思っていたが、西洋でもワンピースが流行っているというのがまったく理解できない。私にとってスティーブンソンの『宝島』は岡本綺堂の半七であり、ワンピースは里見浩太朗主演の半七のようなものだ。
出版社や放送局にとって一番おいしいのはそういうまがいものをありがたがる視聴者であって、そういうマンネリ化して冷め切ったコンテンツをただだらだらと提供することが、一番楽に金儲けできることなのだからどうしてもそれが世の中の定常状態とならざるを得ない。それを非常に不幸なことだと思っているのはごく一部の少数派なのだろう。
さらについでだが、私にはNHKの大河ドラマがつまらなくてどうしようもないのだが、人はみな、しかもある程度歴史や文芸に詳しい人までが、大河ドラマを熱心に見ている。不思議で仕方ないのだが、マンネリとか定常状態をありがたがる一種の群衆心理と関係があるのだろう。人は社会的な生き物なのでみんな盆やクリスマスや正月を人と同じようなやり方で過ごしたがるし、人が死ねば葬式に行きたがるし、人が結婚すれば結婚式に行きたがる。大河ドラマに紅白歌合戦にNHK。そういう人間心理を利用したメディアなのだ。いやメディアとはもともとそういうものなのだろう。
例えば半七捕物帳だと、湯島聖堂で素読吟味というものがあり、武家の子弟にも将軍に謁見を許されたお目見え以上の旗本とそれ以下の御家人の間で喧嘩がある、というようなことが下敷きになっている。こんなことは岡本綺堂の頃にはまだ常識に属することであったかもしれないが、野村胡堂の頃までくるともう恐ろしく古い時代のおとぎ話みたいになってしまっていただろう。で私にはそうした下敷きの部分が面白くて仕方ないのだが、それは私が60まで年をとったせいに違いなく、普通の人にはまったくもって余計な前振りに過ぎないのだろうと思う。スティーブンソンの『宝島』に出てくる黒丸という印象的な小道具も、私には非常に興味深いが、ワンピースの読者らにとってはどうでも良いことなのだろう。