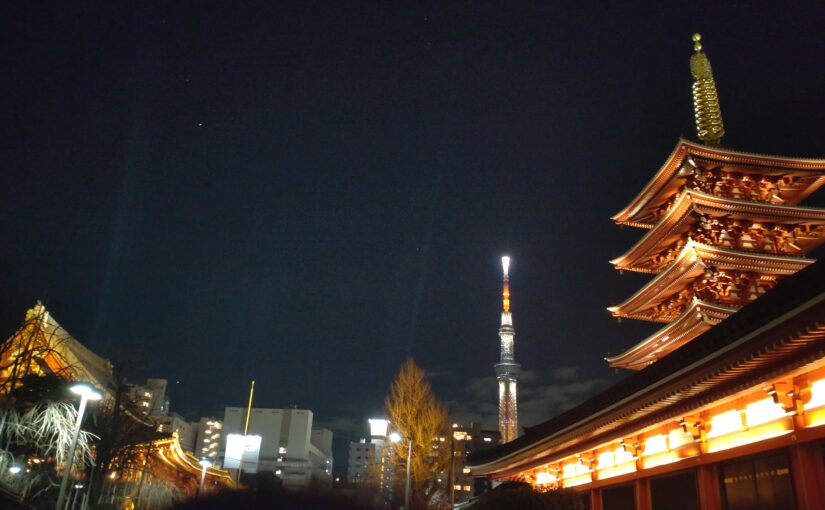土曜日に風邪を引いて火曜日から入院なんで(笑)、体調を整えるため寝てばかりいる。wordpress のバックアップを取ったり、そのためのシェルスクリプトを書いたりと、なんかあったときのために備えたりもしている。入院といっても以前にもやったアブレーションの手術なんで、よっぽどのことが無い限り生きて帰れると思うんだが、心臓の持病のおかげで結構頻繁に、そうねだいたい3、4年に一度くらいの頻度で入院してて、しかし職場は遠慮無く多忙な役職を当ててくるので定年前にすでに人生に諦念していたりする。もうこれからは終活以外やらん。新しいことをこれから始めたりはしない。1年半ほどかけて本を書き推敲し書き足し書き直ししてきて仕上げたばかりなのだが、こんなに長い時間1冊の本を根詰めて書くというのは、実を言えばもう二度とやりたくない。文字すかすかの新書くらい(せいぜい5万字くらい?)なら半年に1冊とか書こうと思えば書けるかもしれんが。25万字の本は書くべきではない。長ければ長いほどだんだん何を書いてるかわからなくなってくる。一カ所直すとほかの箇所にも影響するから、何度も全体を見直し書き直さなきゃならない。25万字を何度も何度も校正するのは正直うんざりする。1度か2度ならともかくとして根気が続かない。いろんなことを付け足したりしていつまでたっても終わらない。無限ループだ。とまあそんなことは実際に書いてみないと体験できないからみんな一生のうちに一度くらいは書いてみると良い(笑)。
とか言いながら「エウメネス」なんかはあれ50万字くらいあるんじゃなかろうか。われながらすごい長編小説を書いたものである。
和歌は31字しかないからほぼ完璧に推敲校正できる(可能な文字の組み合わせをほぼすべて試してみることができる)。25万字とか50万字だと、どんなに推敲しても決して完全には直せない。歌詠みから見れば歌にくらべて小説や評論なんて、どんなに頑張っても10%、せいぜい 30%くらいの完成度にしかならない。もし和歌と同じクオリティで50万字の小説を書いたらものすごい文章ができあがるに違いない。ゲーテはファウストを全部韻文で書いたというが要するにそれくらいやったとしても、せいぜい50%くらいの完成度ではなかろうか。
自分としてはやれることは完全にやりきった感が今回は非常に強いので、一度徹底的にやると飽きてもうやらんでいいかなと思うタイプなので、もしやるとしたら「エウメネス」「関白戦記」あたりを手直ししたいが、実をいえばこれらももう直す必要ないんじゃないか、というより、直したほうが良いには良いのだろうが未完成のまま遺して死んでも別に大差ないのじゃないかと思っている。「関白戦記」はたぶん完成度は高いと思うなあ。誰も読んでくれないけど。
村上春樹は小説を書くというのはジャズのインプロビゼーションみたいなもんだと言っていたが確かに長編小説というものはそんなふうな気分で書かないと書けないだろうし読者も読めないだろうと思う。音楽のように最初から最後まで時系列にするすると飲み込んでいくのであればいい。最初に読んでいたことは半ば忘れていても後の方も自然に読めるんならいいが、途中まで読んでだんだんわかんなくなってきて、最初に戻って読み直してみなきゃわからん、みたいな複雑な構成になっているとものすごく疲れてしまう。「エウメネス」なんて登場人物が何百人いるかわからん。普通こういう小説を人は読めぬものだ。書くのも難しい。私の中では何百人もいる登場人物の個性を一人一人書き分けているつもりだが、読んでいる人がわかっているかどうか自信はまったくない。バルシネ、アルトニス、ラオクシュナ、アマストリー、アパマ、キルケー、ピュティオニケ、オリュンピアスなどなど、みんなひとりひとり描き分けているつもりでいるんだが、どこまで理解されているんだろうか。
逆に登場人物が二人かせいぜい三人でストーリー展開もゆっくりで、しかも音楽を聴くように楽しみながら読めるのであれば、誰でも読めるだろう。村上春樹の読者があれほど多いということはそういう仕組みになっているのだろうと思われる。
いつも思うのだがなんで私はこんなふうな人間になったんだろう、なんでこんな仕事をしてこんなふうな執筆活動をしてこんなふうに死ぬのだろうか、実は私はもっと違う人間として生きて死ぬはずだったんじゃないかという気持ちが強い。なので、五十代になってから作曲を始めたりしてみた。まだなんか自分に試していない可能性があるんじゃないか、死ぬ前にちょっと試しておこうという気持ちがあった。しかしもう六十なので、逆にもうこれ以上ジタバタと諦め悪く往生際悪く無駄な努力をしたくない。定年過ぎているのにいつまでも仕事に未練たらたら昔の職場に顔出す人をよく見るが非常にみっともない。退職したらすっぱりやめりゃあいいのにと思う。働いているうちに定年後のことなど何も考えてなかったのかとも思う。
私は32才まではわりとまっすぐ生きてきたが、それから迷走し始めた。では32才のときに転職して全然違う人生を選ばなきゃよかったのかというとそれも違う気がする。転職するにしても全然違う転職の仕方はあり得た。というより32才で死んでても別に私の人生に大した違いはなかった気もする。46才で大病を患ったがしかし46才で死んだところで私の人生に大した違いはなかった気もする。明治天皇は59才で死んで私もいま59才だが、今死んでも私の人生大した違いはない気がするがしかし、今準備している本が出版されてそれが世の中にどんなふうに受け止められるか確かめてから死にたいとも思う。
70才、80才まで生きてもあんまり意味はない。払った年金が返ってくるからできるだけ長く生きたほうが得だ、長生きした方が勝ちで早く死ぬと損だとしか思わない。若いときとちがって体が動いてくれないから生きていてもさほど面白くない。やりたいこともあまりない。長生きして引っ越しなどして新しい出会いがありゃそれはそれで楽しいんだが、しかしいつまでも生き続けられるわけではないのだからそれもどうでも良いといえば良いことだ。
でも私もこれまでいろんなものを書いてきたから次に出る本がそんなに世間の注目を集めるはずもないってことは99.9%くらいは言える。でも0.1%くらいの可能性はある気がしている。私が生きているうちには理解されなくてもそのうち理解してくれる人が出てくる可能性はもっとあるように思われる。