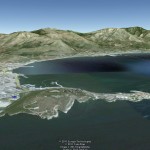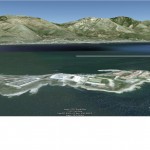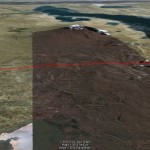あれ、「しわい」は方言ではなくて普通に「けち」と言う意味の古語だと思って調べてみると、
岩波古語辞典によれば『驢鞍橋』という、鈴木正三の言行を弟子が記録したものに出るらしい。ということは、江戸初期くらいからの言葉だろうか。
月: 2012年1月
養子
昔の人の経歴を調べていて感じるのは、養子縁組というのが、非常に多かったということだ。
例えば自分が次男・三男などで、親戚筋、特に本家などに嫡子がいない場合に、
養子となってその家の家督を相続する。よくあることだったようだ。
独身で子供がいない、ということは当時としては滅多になかったようだが、
実子がいない、
実子がいても娘しかいない、
実子はいたが早死したり病気だったりして嫡子にはなれない、
あるいはなんらかの理由で廃嫡した、
などということはしばしばあった。
息子はいないが、娘はいる場合には、婿養子を取る。
その場合も通常は親戚の男子を優先するのだろうが、
特に学問や芸能の家の場合には、有能な弟子を婿に取ることが多かったようだ。
娘もいない、親戚にも適当な子がない場合は、
まったく赤の他人を養子にすることもあったように思われる。
その際には、赤の他人が赤の他人の嫁をもらう、というのではなく、
親戚の娘を養子にしてその婿養子をとるとか、
あるいは養子に親戚の娘を嫁がせるとか、
そんな工夫をしたのではなかろうか。
ともかくそういう具合に養子で成り上がった人というのが少なくない。
家というのが重要かつ根本的な社会組織であり、
そこには家業とか所領とか財産とか株とか組合など、誰かに相続しないわけにはいかない資産が付随する。
一方では子沢山な家庭があり、
他方では子宝に恵まれない家があり、
かつ家業の優秀な後継者が欲しいという状況では、
さかんに養子縁組が行われてきたのだろう。
一度養子制度というものをきちんと調べる必要があると思う。
王家
天皇家を王家という言い方がどうかというので盛り上がっているようだが、
『日本外史』に限って言えば、
> 先王の必ず躬ら之を親らしたまふは、其の旨深し。
> 吾外史を作り、はじめに源・平二氏を敍するに、未だ嘗て王家の自ら其の権を失ひしを歎ぜずんばあらず。
> 吾は王族なれば、当に天子と為るべし。
> 我、平治年間より功を王室に建て、天下を專制し、位、人臣を極め、帝者の外祖と為る。
> 汝、王命を奉じて乱賊を討ち、兵を交へずして帰る。
などのように、天皇を「王」と呼ぶことは極めて普通。
漢文にはそういう風習がある。
また、
> 平氏は桓武天皇より出づ。
のように、「天皇」という呼称を使うこともある。
ただし、普通「王」といえばそれは「親王」のことを意味するから、天皇を単に王と呼ぶことはあり得ない。
「王命」とか「王室」のような熟語の中で使われるだけだ。
他には「上皇」「院」「法皇」なども普通に使われている。
天皇を「日本国王」と呼ぶことも忌避されるだろう。
というのは、これは慣習的には「中国皇帝」の臣下としての呼称であり、
足利義満もそう呼ばれていたからだ。
思うに、「王家」という言い方は少し漢文的・儒学的であり、口語で使われることはまずなかっただろう。
公家の日記も漢文だから、使われていた可能性は高い。
公式文書では「王家」や「王族」などが簡潔で好まれたのではなかろうか。
「皇室」や「皇族」などという用語はあまり使われなかったのではなかろうか。
大和言葉なら、天皇家の血統という意味なら「あまつひつぎ」だろうか。かなり堅苦しいが、他にあまり思いつかない。
じゃあ普段の話し言葉ではなんと言っていたか。
さあ、わからない。
だが、現代語で話すドラマなのだから、現代人の口語に準じればよいだけではなかろうか。
ガエータ
[google earth 画像の使用](http://support.google.com/earth/bin/answer.py?hl=ja&answer=21422)
によれば、
> Google のロゴの帰属を含む、著作権および帰属を保護するという条件で、このアプリケーションからのイメージを個人的に (ご自身のウェブサイト、ブログ、またはワード文書などで) 使用することができます。
ということなので、どんどん使わせてもらう。
ガエータなんだけど、google の航空写真では、城塞の部分がちょうどつなぎめになっていて、
二重にぶれたようになってしまっている。
それで適当に重ねてみると次のようになる。
複雑な形をしているのだが、
おおまかには、
中庭をもつ二つの矩形の砦がくっついたような構造になっていることがわかる。
ガエータは全体としては函館のような地形をしていることがわかる。
その突端に砦があった。
また港は軍港であって、アメリカ海軍の母港にもなっている。
米軍にとってはイタリアの首都ローマ最寄りの便利な港だろう。
日本の横須賀みたいなものか。
マラズギルト
[Battle of Manzikert](http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Manzikert)や
[Alp Arslan](http://en.wikipedia.org/wiki/Alp_Arslan)、
[Roussel de Bailleul](http://en.wikipedia.org/wiki/Roussel_de_Bailleul)
などを丹念に読んでわかることは、マラズギルトの戦いというのは、
残された記述には矛盾や不完全なことが多く錯綜しているということと、
史実のまま小説にしてもごちゃごちゃしすぎてあまり面白そうではない、ということだ。
だから適当に脚色するしかないと思うが、一応史実は史実としてきちんと把握しておかねばなるまい。
> In 1071 Romanos again took the field and advanced with possibly 30,000 men, including a contingent of the Cuman Turks as well as contingents of Franks and Normans, under Ursel de Baieul, into Armenia.
> Ursel de Baieul was a Norman adventurer (or exile) who travelled to Byzantium and there received employ as a soldier and leader of men from the Emperor Romanus IV.
> he was was sent into Asia Minor again with a force of 3,000 Franco-Norman heavy cavalry.
クマン・トルコとはキプチャク平原にいたトルコ人。
後は、フランク人とノルマン人の傭兵。
ウルゼルはノルマン人の隊長。ノルマンディから逃げてきたか旅してきた。
おそらくライン川とドナウ川をたどってコンスタンティノープルまで来たのだろう。
ロマノス軍は、東ローマ人、トルコ人、フランク人、ノルマン人などで構成されていた。
> At Manzikert, on the Murat River, north of Lake Van, Diogenes was met by Alp Arslan. The sultan proposed terms of peace, which were rejected by the emperor, and the two forces met in the Battle of Manzikert. The Cuman mercenaries among the Byzantine forces immediately defected to the Turkish side; and, seeing this, “the Western mercenaries rode off and took no part in the battle.” The Byzantines were totally routed.
フランク・ノルマンの傭兵は参加しないだろうと見たトルコ傭兵はセルジュークに寝返ったとある。
Manzikert はギリシャ語であり、トルコ語では Malazgirt、イラン語では Malāzgird または Manāzgird、
アラビア語では Manāzjird などとも言うらしい。
いずれにしても、このアナトリアともアルメニアとも言うべき土地は、古代ギリシャ人が住んでいた場所からはかなり外れており、
地名をギリシャ語読みにしなくてはならない義理はない。
よくわからんのでマラズギルトで良いのではなかろうか。マラズギルドと書いても間違いではない。
気になったのは、マラズギルトからアララト山は見えるかということだった。
近頃は現地に行かなくても google earth でだいたいの眺望は把握できる。
マラズギルトはヴァン湖の北、ムラト川のほとりにあるというが、
google map で見ると、山から幾つかの川が流れでて、平原で合流する辺りにマラズギルトの町はある。
アナトリア高原の中の扇状地のような場所だろう。
で、おそらくアララト山は見えるのだが、160km は離れている。標高5000m あっても、少し遠すぎる。
たぶん東京から富士山を見るくらいの大きさである。
マラズギルト要塞の場所には、当時の城塞跡かは知らないが、記念公園があるようだ。
アララト山は見えないが、東の、ヴァン湖の近くに大きな[Mount Süphan](http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_S%C3%BCphan)
という山が見える。
これはアナトリアでアララト山の次に高い山だそうだ。
アフラートは、ヴァン湖畔にあり、マラズギルトはそこから北へ、そうとう険しい山岳地帯を越えて 50km くらいのところにある。
アフラートからマラズギルトへ救援に向かうには、二日か三日はかかるだろう。
左図の一つ目は、google earth で、正面に東のシューファン山、右手にヴァン湖があって、
マラズギルト(左)とアフラート(右)を線で結んだものである。
二つ目はヴァン湖畔のアフラートから山を越えてマラズギルトを見たものであり、山がそうとう険しいことがわかる。
[Ahlat](http://en.wikipedia.org/wiki/Ahlat)
> Ahlat and its surroundings are known for the large number of historic tombstones left by the Ahlatshah dynasty.
アフラートにはマラズギルト戦後にセルジューク朝による大規模な入植があった拠点の一つ、
少なくともセルジューク王族の都の一つのように思われる。
ロマノスはアフラートへ[Joseph Tarchaneiotes](http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Tarchaneiotes)を派遣した。
彼の軍勢がどうなったかはわからない。
アフラートを取ることもなければ、マラズギルトに向かいもしなかった、
ともかく行方不明になってしまったようだ。
> Romanos was unaware of the loss of Tarchaneiotes and continued to Manzikert, which he easily captured on August 23
1071年8月23日、ロマノスはタルカネイオテスが行方不明になってしまったことを知らぬままマラズギルトを簡単に落とした。
> The next day some foraging parties under Bryennios discovered the Seljuk army and were forced to retreat back to Manzikert.
翌24日、先遣隊がセルジュークを発見し、マラズギルト要塞に撤退した。
> The Armenian general Basilakes was sent out with some cavalry, as Romanos did not believe this was Arslan’s full army; the cavalry was destroyed and Basilakes taken prisoner. Romanos drew up his troops into formation and sent the left wing out under Bryennios, who was almost surrounded by the quickly approaching Turks and was forced to retreat once more. The Seljuk forces hid among the nearby hills for the night, making it nearly impossible for Romanos to send a counterattack.
アルメニア人の将軍というのは現地テマのローマ人ということだろう。
ロマノスに命じられて出撃した彼はセルジュークに捕らえられてしまい、
ロマノスもマラズギルトまで撤退した。
セルジュークは丘のかげに隠れて反撃を防いだ。
> On August 25, some of Romanos’ Turkic mercenaries came into contact with their Seljuk relatives and deserted.
翌25日、トルコ人傭兵はセルジュークの側に寝返っていなくなった。
> Romanos then rejected a Seljuk peace embassy
ロマノスはセルジュークの和平交渉を拒絶。
> The Emperor attempted to recall Tarchaneiotes, who was no longer in the area.
ロマノスはアフラートへ向かわせた軍勢を戻そうとした。
> on August 26 the Byzantine army gathered itself into a proper battle formation and began to march on the Turkish positions
翌26日、ロマノスは態勢を整えてセルジューク軍へ向けて進撃した。
> Andronikos Doukas led the reserve forces in the rear
アンドロニコスは予備の軍団とともにロマノスの後方にいた。
> The Byzantines held off the arrow attacks and captured Arslan’s camp by the end of the afternoon.
東ローマ軍は昼までにセルジューク陣営まで進んだ。
セルジュークは遊牧民族特有のヒットアンドアウェイ戦法でローマ軍を翻弄し、
ロマノスは日が暮れる前に撤収しようとしたが、
アンドロニコスはロマノスを援護せず、勝手に戦線離脱した。
セルジュークはこの機会を利用して反撃。
結局この日、ロマノスはセルジュークの捕虜になってしまった。
花札
『虹の深淵』というタイトルの小説を書こうかと思っている。
これは江戸時代の風俗を描いているが、実際には現代日本の二次創作の闇について書きたいのである。
しかし今の時代を描くのはあまりにどろどろしてしまうので、江戸時代ということにするわけだ。
それで花札など調べてみた。
江戸時代町奉行の管轄ではない、旗本屋敷や寺社や公家の家などで賭博が開かれていたという。
寺銭などというのがそれだ。
また公家は内職として花札やいろはかるた、百人一首の歌かるた、などを制作していたという。
二条派の歌というのは二次創作そのものであり、類題集を元ネタとして、
同工異曲の歌を無限に再生産する遊びだ。
そのへんの、公家の底辺社会の闇というのも、実に深くおどろおどろしいわな。
書かない方が良いかもしれん。
でもネタとして思いついたということはここに記しておこう。
この時代のそういう世界を描くにはどうしても、宣長や盧庵や景樹も書きたくなるに違いなく、
そういうくくりの中のエピソードして書くことにするかもしれん。
それで、
ネットで花札をぐぐってると天正カルタとか[うんすんカルタ](http://nippon-kichi.jp/article_list.do?p=5799)などが出てくるのだが、
これらは絵柄がおいちょかぶ用の花札、つまり[株札](http://www.amazon.co.jp/%E4%BB%BB%E5%A4%A9%E5%A0%82-%E6%A0%AA%E6%9C%AD-%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98/dp/B000CNF0AK/ref=sr_1_10?s=toys&ie=UTF8&qid=1325983331&sr=1-10)に似ている。
株札は花が描かれてないから花札ですらない。
私らが子供の頃は『じゃりん子チエ』の真似をして花札でカブをやったりしたのだが、
あれは数字が書いてないから覚えにくい。
花札というのはたぶんだが、幕府の禁制から逃れるために、
トランプやうんすんカルタなどに特徴的な数字や記号を消し去ったのだろう。
ただし何月がどの絵柄かを知っている人にはトランプとして使用することもできる。
日本人がトランプを和風におくゆかしくアレンジした、のではなくて、
単なる賭博逃れだったと見た方が当たっているだろう。
おいちょかぶは数字がわからんと面倒なんで、それ専用の、つまり賭博専用の札として、
アングラな世界で生き残ったのだとすれば話が通る。
うんすんカルタだと、縦や斜めに交差する剣や杖、あるいは棍棒が描かれているが、
かぶ札だとそれが真っ黒な帯で描かれている。
また株札には南蛮人の絵も描かれているが、これなどもトランプの絵札の名残なのだろう。
関西では割に一般的に使われてるというが、やはり、
江戸よりは禁制が緩かったためだろうか。
二次創作
今の世の中にあふれているのは、どれも一次創作のふりした二次創作だわな。
続編とかもある種の二次創作だしな。
著者が死んでもスタッフだけで制作は永遠に続くしなあ。
そんなんばっかだわな。
同人なんて二次三次は当たり前でひどいと十次二十次。
要するにマーケティングで消費者の方ばかり向いてりゃそうなりますわな。
消費者が自分で制作する場合も同じだな。
消費者にも、創作はできないけど、好きな作品の再生産はできるわけよね。
二次創作ばかりだと嘆く人もいるようだが、どうせ昔から同じだよ。どこの世界でもどこの国でもいつの時代でも。
今の日本に限ったことじゃない。
あとはオリジナルなものでも単発的な私小説みたいなやつ。
ネットでみかけるおもしろい話とか全部そう。
確かにね、事実は小説よりも奇なりですよ。
だが、そんな一発撃てばおしまいみたいなネタは創作とは言えんよね。
だから、私は私小説は好きじゃない。
自分をさらけ出すのも好きじゃない。
素人に私小説書くのを勧める人もいるようだが。
逆に二次創作のふりをして一次創作になってるのも割とある。
『キル・ビル』や『エヴァ』なんかはその典型かもしれん。
芥川龍之介も、今昔物語を素材にしていろいろ実験したわけだし。
いきなり一次創作するのは難しいし、また、他人に読ませようというときに読めない、読んでくれない。
だから、歴史とか古典文学を借りる。
しかしそこには一次的な実験が盛り込まれている。
まあ、私の書いたものもほとんど『平家物語』そのままだったり、為永春水『春色梅児誉美』や高崎正風『歌ものがたり』そのまんまだったりするんだけど。
だって同じことをあの芥川龍之介だってやってるじゃん。
それにほとんど忘れられた古典を掘り起こすのだって意義のあることだよ。
『平家物語』にしたって、私の場合義経とかは完全にスルーしてるしね。
有名過ぎてつまらんのよね。
古典のリメイクとかオマージュというものはね、二次創作とは違うものなんだよ。
しかし、普通に読んだ人には違いがわからんよな。
オリジナルの劣化版にすら見えるかもしれんね。
よくあるパターンとしては、イケメンとフツメンとブサメンがいて、ヒロインが何人かいて、
ああだこうだがあって、結局主人公(通常はフツメン)がヒロインとくっつくとかいう、そんな決まり切った、水戸黄門的サザエさん的な展開がありましてね。
そうすると読者も予定調和的に安心して読めると。
そういう需要が非常に大きい。
そして、そういう制作ならば素人にもまねできる。作者側に参加できる。
市場も結局そこらピンポイントにモノを出してきて、反応が未知の読者は最初から相手にしない。
今までないような、よくできた作り話を作りたいわけですよ。
ああよくできてるなこの作り話。って思ってもらいたいわけよ。
ありきたりな、ステレオタイプやキャラを使い回して、既存の客層にむけて書くのではなくてね。
そう、新たな客層、あらたな市場を作り出すのがほんとにオリジナルな作品でしょう。
それもできないんじゃ、わざわざ書いてる理由がないわ。
さっさと見切りつけてもっとほかのことやるだろう。
ところで、パブーに自分の書いたものを公開しだしたのは、
2011年の4月からなんだよね。
まだ一年たってない。
その中で一番PVが多いのが『棟梁三代記』で次が『スース』。
なんで?と思う。
『棟梁三代記』は、たぶんだが、公開した時期が早いのと、頼朝、清盛、実朝などといった有名人が多く出てくるので、検索にひっかかりやすいのだろう。
『スース』が多いのは、これも推測だが、ある人をモデルに使ってその了解を得たから、その関係者がたくさん見にきているのではなかろうか。
こちらはそんなに検索にひっかかるような内容ではないしな。
または、『スース』は七つに分かれているので、それぞれに検索でひっかかったやつが最初から読んでみようとか、ラストが気になって読んでみるとか、
そんなのかもしれんね。
ただ、『棟梁三代記』『スース』みたいのが、私の書いたもののなかで、ほんとに好まれてる傾向があるとすると、
これはどう解釈すればよかろうか。
風雅集
岩佐美代子『風雅和歌集全注釈』を読み始めた。上中下三巻たっぷりある。
も少しコンパクトでもよかったのだが、まあいいや。
為兼
> 降る雪も山もや変はる変わらじを心よりこそ春は立ちけれ
> 今日に明けて昨日に似ぬはみな人の心に春の立ちにけらしも
> しづみはつる入り日のきはにあらはれぬかすめる山のなほ奥の峰
> 鶯の声ものどかに鳴きなしてかすむ日影は暮れむともせず
すごい歌だな。やはり為兼は別格だ。
貫之
> 春立ちて咲かばと思ひし梅の花めづらしみにや人の折るらむ
わろす。さすが貫之。彼はこういう歌が多いんだなあ。
定家
> なにとなく心ぞとまる山の端に今年みそむる三日月の影
定家は影が好きなんだな。
後鳥羽院
> 朝日さすみもすそ川の春の空のどかなるべき世の景色かな
> 松浦潟もろこしかけて見渡せばさかひは八重の霞なりけり
なんかゴージャスで大いばりな歌だなあ。派手好みな若き帝王って感じだよなあ。
崇徳院
> 春来れば雪げの沢に袖垂れてまだうらわかき若菜をぞ摘む
「うらわかきわかな」とは大胆な反復だなあ。
読み人しらず
> 人ごとに折りかざしつつ遊べどもいやめづらしき梅の花かな
為氏
> 人もなき深山の奥のよぶこ鳥いく声鳴かば誰かこたへむ
光厳院
> つばくらめすだれのほかにあまた見えて春日のどけみ人かげもせず
おもしろいなこれ。わざと字余り。「あまた見えて」でなくて「あまた見え」でも良いはず。
蘆庵と宣長
[宣長年譜1757年](http://www.norinagakinenkan.com/nenpu/nenpu/n0183.html)
> 宝暦7年8月6日 (1757/9/18)
○8月6日 未頃(午後2時頃)より、孟明、吉太郎等と高台寺に萩を見に行く。途中、霊山に登り、四人各一句で五絶詩を作る。正法寺より洛中を眺め、高台寺に廻る。そこの茶店で本庄七郎と連れの男に会い暫く時間を過ごす。その後、孟明と別れ、吉太郎と帰る。祇園町あたりから雨となる。
> 『在京日記』(宣長全集:16-128)。
本庄七郎は、小沢蘆庵。蘆庵は享保8年(1723)生まれで宣長より7歳上。寛政5年(1793)上京の折にも対面、唱和する。その時の蘆庵の詞に「この翁は、わがはたち余りの比、あひし人にて、年はいくらばかりにやと、とへば、六十四とこたふ。そのよの人をたれかれとかたりいづるに、のこれる人なし」とある。宣長が京都に遊学した年には既に30歳であるから「わがはたち余り」はあるいは記憶違いか。蘆庵と宣長の接点は不明だが、新玉津嶋神社歌会の森河の所であろうか。森河、蘆庵共に冷泉為村の弟子である。
廬庵が1757年に宣長と出会い、宣長の『排蘆小船』に廬庵の「ただごと歌」の影響がある、
とすればこれはかなり重大なことになる。
「ただごと歌」の主張と、『排蘆小船』のありのままに歌を詠めという主張は、
いずれも紀貫之の古今序に基づいていて、極めて近い。
廬庵は1723年生まれ、宣長は1730年生まれ。当時、廬庵34才、宣長27才(いずれも満年齢)。
「この翁は、わがはたち余りの比、あひし人にて、」というのは、つまり自分が二十代の頃に、という意味であり、
話のつじつまはあう。
というよりも、宣長はもっと早い時期に廬庵と会っていたかもしれない。
日記に書かれていないだけかもしれないのだから。
宣長は1753年、冷泉為村門下の森河章尹に入門した。
廬庵もほぼこれと同時期に為村の門人になった。
同じ京都の同じ門下である。
これ以後二人がたびたび出会っていてもおかしくない。このとき宣長はまだ23才。
まさに「はたち余り」の頃である。
月次会の席で、少なくとも年に数回は会っており、場合によっては、
個人的に頻繁に連絡を取り合っていてもおかしくない。
このことは、繰り返すが、極めて重大なことなのである。
なんとか証拠固めしたい。
廬庵という人の経歴はわかっているようでまったくわからない。
宣長の場合こまごまと日記をつけていて、それもふくめて著述のほぼすべてが完全な形で残っており、しかも全集としてまとめられている。
正に一次資料・一級資料であり、研究がやりやすいといったらない。
しかし、廬庵のよく知られた六帖詠草などは、割と年を取ってからの歌しか採られていないようだ。
宣長と出会った30才の頃にどんな歌を詠んでいたか、それもよくわからない。
[江戸中後期における三都間の歌壇の対立](http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/UCRC/2006/ja/issue/pdf/pdf_0309city-fiction/07arokay.pdf)。
ドイツの日本研究者が書いたもののようである。
少し面白い。
> 職仁親王とその弟子である谷川士清や特に言語学者として知られている富士谷成章の流派、武者小路実岳と弟子の澄月や伴蒿蹊の流派、そして冷泉為村と弟子の小沢蘆庵、慈延、涌蓮の流派である。後には為村と実岳が激しく競争するようになったが、弟子の澄月と蘆庵が特に対立的であった。
> 大坂の歌壇では烏丸家や有賀長因の歌学を受け入れた加藤景範が中心的存在になり、初心者向けの歌学書を出版したり、京都の歌人である長因・蘆庵・澄月などの歌と自詠を歌集に編んだりした。先に述べた、和歌の普及に功績のあった有賀長伯と同じように、通俗歌学書によって大坂での和歌の普及に貢献した。
なるほど、当時の京都・大阪の歌壇とはこうしたものだったのだろう。
有賀長因は、松坂に帰った宣長が添削を頼んだ有賀長川のこと。
烏丸光栄は為村の師で霊元天皇の弟子。
有栖川宮職仁親王は霊元天皇の皇子で光栄の弟子。
谷川士清は宣長と比較的似た経歴の人で、三重県津の出身で京都で医者となり、職仁親王に歌を習って国学者となった、とある。
宣長のライバルとして描いたら面白そうな人だな。
加藤景範は医師で薬売り。大阪にいたのだろう。
宣長が有賀長川に添削を頼んだのは、長川が弟子をたくさん取って通俗的な添削などを商売とするような人だった、
というだけのことだったのではなかろうか。
ある意味、後の香川景樹に似てはいないか。
富士谷成章は京都生まれ、職仁親王の弟子で国学者、宣長は彼を評価していたようである。
武者小路実岳は堂上家。
伴蒿蹊は京都の商家の出。
澄月は子供の頃上洛して比叡山に登り僧となったようだ。
慈延も似たような境遇の人のようだ。
涌蓮は伊勢の人で江戸にいたが出奔して京都・嵯峨に住む。
[小沢蘆庵の人となり・事績](http://www.sobun-tochigi.jp/hurusato/matome.html)
> 小沢家は大和宇陀郡松山藩。
> 享保8年(1723)難波に生まれ、京都に住した
> 若き時本庄家の養子となり、本庄七郎などと称した。
> 武技にも長じ、鷹司輔平に仕えたが、致仕後は歌人として一生を送った。はじめ冷泉為村を師としたが、破門後一家の説を立て、巧まぬただ言を主張し、清新平坦しかも雅趣ある作品を残した。
> 澄月・慈延・伴蒿蹊・上田秋成・入江昌喜・加藤千蔭らと交友があった。
> 晩年契沖を尊び、その著書を集め翻刻の意があった。静嘉堂文庫蔵『さいうの記』21冊には契沖説の書抜が多い。
流布の刊本『六帖詠草』のほかに稿本『六帖詠藻』47冊(自筆本静嘉堂文庫蔵)やその系統の本もまた知られている。
著書としてほかに『ふり分髪』『ふるの中道』などがある。※阿部註:編著書類は50書にのぼる。
宇陀というのは、大和の飛鳥の辺り。南紀の山間部、といったほうがわかりやすいだろう。
そこの武士の子孫として大阪に生まれ、のちに京都に移り住んだ。
養子となり、士官もしたが、四十代半ばに浪人になっている。
それ以上のことはわからん。
上田秋成との交友とは晩年近くのことだろう。
入江昌喜は大阪の商人で、隠居後に国学を研究した。
加藤千蔭は有名な江戸の文人で、御家人。馬渕や田安宗武などの一派だわな。
おそらく書簡上のつきあいで、盧庵と直接会って交友したわけではあるまい。
上の引用の中には入ってないが、香川景樹とも交際があったはずだ。
排蘆小船
『排蘆小船』だが、万葉集に出てくる
11: 2745 湊入之葦別小舟障多見吾念公尓不相頃者鴨
(湊入りの葦別け小舟障り多み吾が思ふ君に会はぬ頃かも)
12: 2998 湊入之葦別小船障多今来吾乎不通跡念莫
(湊入りの葦別け小船障り多み今来む吾をよどむと思ふな)
或本歌曰 湊入尓蘆別小船障多君尓不相而年曽経来
(湊入りに葦別け小船障り多み君に会はずて年ぞ経にける)
から来ているとする説が一般的だが、しかし、和歌データベースで検索すると、37件もあって、後世の勅撰和歌集でもしばしば使われていることがわかる。
題しらす 人まろ みなといりの葦わけを舟さはりおほみわか思ふ人にあはぬころかな
(拾遺)
辛しなほ葦別け小舟さのみやは頼めし夜半のまた障るべき
(続拾遺1279年)
おくれても葦別け小舟入り潮に障りしほどを何か恨みむ
(続後撰1304年)
道あれと難波のことも思へども葦別け小舟すゑぞとほらぬ
後嵯峨院 (同上)
澄む月のかげさしそへて入り江漕ぐ葦別け小舟秋風ぞ吹く
為藤 (後千載1320年)
うきながらよるべをぞ待つ難波江の葦別け小舟よそにこがれて
(新千載1359年)
同じ江の葦別け小舟おしかへしさのみはいかがうきにこがれむ
為世 (同上)
以下略。で、このように「排蘆小船」なる言い回しが頻繁に使い回されているのは、三代集の一つ『拾遺集』
の中に、柿本人麻呂の歌として一首採られているからであろう。
宣長が万葉集をこの時期に直接読んでいたとは必ずしも言えない。
三代集ならば和歌を志すものは誰もが直接読んだはずだ。
意味としては、学問の道に障害が多くてなかなか先へ進めない、ということを言っているだけだと思う。
おやおや、頓阿が『草庵集』で何度も「葦分け小船」を使ってるぞ。これはもしや、宣長は『草庵集』を読んだだけかもしれんね。
なみのうへの-つきをのこして-なにはえの-あしわけをふね-こきやわかれむ
こきいつる-あしわけをふね-なとかまた-なこりをとめて-さはりたえせぬ
なみのうへの-つきのこらすは-なにはえの-あしわけをふね-なほやさはらむ
ありあけの-つきよりほかに-のこしおきて-あしわけをふね-ともをしそおもふ
なにはえの-あしわけをふね-しはしたに-さはらはなほも-つきはみてまし
さりともと-わたすみのりを-たのむかな-あしわけをふね-さはりあるみに
しもかれの-あしわけをふね-こきいてて/なみまにあくる-ゆきのとほやま
ところで、『排蘆小船』は、「もののあはれ」論の原型であるとして、
『安波礼弁』を起稿し、『源氏物語』の講釈を開始した、帰郷後の宝暦8(1758)年頃に成立したのではないか、
宝暦9(1759)年に書いたんじゃないかという説もあるが、
そんなに後ろに引っ張ることはないんじゃないか。
なんでもかんでも「もののあはれ」で解釈したがるのは悪い癖だ。
歴史的仮名遣いがまだからきし使いこなせてないことや、内容がまだそれほど国学っぽくないところをみると、
かなり早い時期、つまり、小沢廬庵と二人で、冷泉為村の悪口を言い合ってた時期に書いたものではなかろうか。
つまり、宝暦7(1757)年8月頃、京都遊学最後の最後の頃。
『排蘆小船』は問答集の形を取っているが、その相手が廬庵だと想像するのは楽しいではないか。
も一つ、国文では普通、「あしわけをぶね」を「葦分け小船」「葦別け小船」などと書く。
しかしそれをわざわざ漢文調で『排蘆小船』と書いたのは、儒学者の堀景山の下で、わざわざ漢文で日記を書いていた時期に成立した、
ということを示唆しないだろうか。こういう漢語臭のする題の著書は他に『紫文要領』くらいか。
『源氏物語』をわざわざ『紫文』と言い換えるあたりがいかにも漢語的だ。