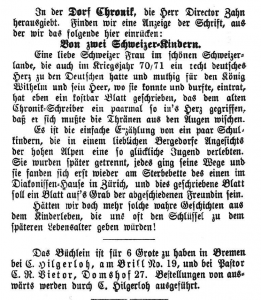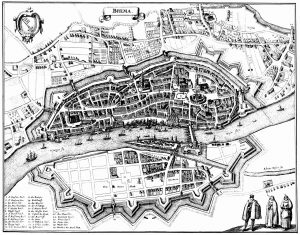5日間の無料キャンペーンの途中だが、もう打ち切っても良いんじゃないかってくらい、
ダウンロードが少ない。
やはり、当初の予定通り、特務内親王遼子3はマンガで出すべきだった。
マンガで出して多少話題性が出れば、そこで小説で完結編を書けばよかった。
しかしまあ自分の中では「原作」を「完結」させることの方に気持ちが傾いてしまった。
「原作」を書き、そこから「シナリオ」なり「ネーム」を書いて、
さらにマンガにしようとしても、ならんわな。
原作をそのままマンガにしようとすると、膨大な背景や小物や登場人物が発生してきて、
作業量的に絶望してしまう。
だから原作は原作として置いといて、マンガは「スピンオフ」とか「外伝」みたいにして作るしかない。
我々はそういう原作のことを世界観などと言うことがある(笑)。
世界観はしかし普通は作者の頭の中にだけあるものであったり、
現物はせいぜいイラストレーション程度しかなかったりするのよね。
というのはふつうの人は一本の小説という形で完成させることはないから。
ましかしもう五年以上小説書いてあちこちに発表しているのに、
私は読者を、固定客をほとんど獲得できてなかったのだからもうこれは仕方ない。
思うに、誰も鶏を飼ってないところで鶏を飼い始めると儲かるが、
みんなが真似して鶏を飼い始めると赤字になる。
同じことはラーメン店でも小説でも言える。
今は誰でも小説書いて発表できるようになった。
KDPの初めの頃は自分もアマゾンで小説売れるようになったってのは少し珍しかった。
しかしいずれ電子の海に埋もれる日が来るってことはわかってた。
もうすでにそれは来た。
誰も鶏を飼わないうちに鶏を飼い始めた人というのが漱石や鴎外なのだよね。
ただ、文芸の場合、いったん古典となってしまうと、
古典は良い悪いという以上の拘束力と影響力を持つから、
強いのよね。それは学術論文と同じ理屈で説明できると思う。
多くの読者を獲得することは力なのだよね。
それは歴史的な継続性を持つ力。
いまも「エウメネス」だけはときどき売れる。
しかし「エウメネス」を買って読んでくれているのは「私の読者」ではない。
エウメネスが出てくる某マンガを読んでいる人たちというのに過ぎない。
エウメネスは私が書いたものの中では割と初期で、
その後何度も書き換えたから、まあそんなに悪いものではないが、
私が書いたものの中でベストだとは思ってない。
で、エウメネスなりなんなりを読んで私の読者になってくれた人。
ほとんどいない。
それはもう結論が出ている
(同じくシュピリの読者は私の読者ではない)。
売れるか売れないかということで言えば需要と供給の関係でしかない。
チラシの裏か裏でないかということも同じだ。
KDPとかpixivとかが出てくる前は、私たち素人にも、
いや出版業界の玄人でも、本だけは違う、良いものを書けば売れるはずだ、
という幻想があったのかもしれない。
しかし電子出版の現実を直視すれば、本もラーメンも鶏も同じだってことは明らかだ。
都議選ですらそうだ。
例えばスタンダールの長編小説だってああいうのがかつては需要に対して、
供給が追いつかなかったから売れたわけだ。
今も多少は需要があるだろう。しかし供給が多すぎる。
供給が多すぎる状態で有効なのはマーケティングだろう。
KDPもまたすでにマーケティングが成熟してきている。
じゃああなたもちゃんと投資してマーケティングやりますかと言われて、
やるはずがない。それは私の仕事じゃない。
昔ダウンロードしてくれてた人も実際には読んでさえいなかっただろう。
今回ダウンロードした人は一応読む気でダウンロードしたのだと思う。
その実数が見えた気がする。
まあ、この五年間で経験値だけは少しあがった。
今まで書いてきたものは遺言代わりくらいにはなるだろう。
文芸は映像や音楽とは違う。
しかし必ずしも棲み分けているわけではない。
セリフの無い手描きアニメーション作品とかPVみたいな小説を書く人がいる。
例えば村上春樹なんかはそうかもしれない。
それもまた文芸である。
そして音楽やアニメーションが好きな人は、
くどくどした台詞や説明がないそういう「空虚」な小説を好むだろう。
台詞や説明が多いアニメーションを揶揄してセツメーションというらしい。
台詞が無いアニメーションの方が高級だと考えているアニメーターは
(非商業アート系には特に)多い。
私は今までそういうものに鈍感だったかもしれない。
今まで文芸作品は文字や台詞だと思ってた、
映像や音楽とは別のメディアで表現手段だと思ってたが違うかもしれない。
ある程度書いて書き込んでみて読者の反応をみたからわかったことだ。
でまあ、20歳くらいで作家デビューするような人は(もともとそういう環境にいて)、
そんなことは最初からわかっているはずなのだ。
もちろん説明や台詞のないアニメーション作品にはある種の限界がある。
私はそういう限界を好まない。
二人か三人しか登場人物がいなければ台詞は無くとも作品は成立する。
メッセージを伝えることはできる。
私が書きたいものはどちらかといえばそういうものではない。
そういう意味では和歌のほうが、私はもっとずっと前から詠んでいたので、
少し実感しやすい気がする。
もう30年間、途中長いブランクがあるが、和歌は詠んでいた。