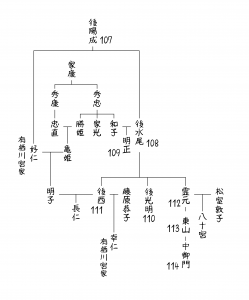[「自分の資産・貯蓄に満足」4割強、高齢者ほどより満足に](http://www.garbagenews.net/archives/2003877.html)
という記事を読んで思ったのだが、
高齢者だからといって自分の資産に満足しているわけではないと思う。
ただ、もう後10年か20年しか生きられないというのに金儲けや出世なんかで無駄に時間を費やしたくないだけだろう。
40歳くらいまでなら、自分の将来に不安があるし、
自分がどこまでやれるか試してみたい気もあり、
また体も動くから、
貯金も資産もこれで十分という気持ちにはなれない。
しかし50歳くらいで体を壊したりしていつ死ぬかもしれんと思えば、
あくせく仕事をするのがばからしくなる。
今日寝て明日の朝は目を覚まさないかと思うと、仕事なんてどうでも良い気になる。
というか定年後も、老後の金は足りているはずなのに、
パートタイムのような形で仕事を続けたり、名誉職みたいな形で仕事にしがみついてる人がいるが、
ああいうのの気がしれない。
たぶん自分が職場で必要とされていると思いたいのだろう。
あるいはただの名誉職なのに偉くなった気分になれるのだろう。
不思議としかいいようがない。
だいたいそういう連中ほど典型的老害で社会の邪魔であって、
さっさといなくなったほうがいいやつばかりだ。
城山三郎『毎日が日曜日』ってのがそれだわな。ただの仕事中毒。
私なら、死ぬまで働かなくて良い金がたまったらすぐ退職すると思うし、
今の仕事はそれまで給料をもらい続けるためにやってるし、
しかもそれでも私が働かないよりは働いた方が少しは社会のためだろうと思うからやってる。
しかしまあ自分で小説売ってみるとわかるが、世の中は営業しないとものは売れない仕組みになっている。
営業さえすれば「風たちぬ」のようなつまらん小説も売れるわけだ。
あほかと思う。
「半沢直樹」とかはまあ、それとは少し違うタイプかもしれんが、
しかし一度当たると原作の小説が馬鹿みたいに売れる。
銀行マンが町工場の技術までちゃんと勉強して融資をするとか言う話が何か美談のように書かれているらしいが、
そんなのは当たり前なんじゃないの。
逆に、私などは、営業なんてのは技術もわからんしアートもわからんし、
ああいう連中がなんのためにあんなにたくさんいるのか不思議で仕方なかった。
つまり、技術やアートがわからん連中が仕方なくたくさん群れて、
わざわざ窮屈なスーツきてネクタイ締めて、
そうやってむりやり社会の多数派を形成して、
アーティストやエンジニアを搾取することによって、
金儲けをしているのだくらいにしか思えなかったのだ、
50近くになるまで。
だからアーティストやエンジニアは文系の連中に搾取されないように、
フリーランスのセンスを持つべきだ、営業を営業職に極力任せず自分でやるようにすべきだ。
自然とそういう発想になるわな。
だがまあ今は営業の連中がいる意味というのがなんとなくおぼろげにわかる。
世の中には金持ちがいてその資産を運用して増やす必要がある。
だから一点豪華で投資する。
それにはいまだにマスメディアが都合が良い、ただそれだけだ。
未だロングテールの時代は来ていない。
営業とかマス広告なしで、クリエイターから消費者へ直接モノが渡るようには、全然なってない。
人間社会は未だに成熟してない。
マスメディアなんてしょせんヒトラーの群集心理と同じだ。
21世紀にもなって大衆の購買動機なんて戦前のナチスドイツと何も違わない。
営業が技術もわからんしアートもわからんというのは今もそう思うし、
キュレーターとかジャーナリストとか評論家なんかというのはまだ金融屋よりは目がきくのかもしれんが、
それでもやっぱり大したことはないと思う。
キュレーターでもない営業職がどうしてものの良い悪いを判断するんだ。
わからん。
キュレーターも結局は営業に走るしな。
ちょっと目利きができる営業、くらい。
ていうか営業のセンスのないキュレーターとかプランナーとかいないわな。淘汰されてしまうから。
キュレーションというのも結局はなんか価値のある作品や作家を発見し発掘し、世の中に広めるというのではなく、
ある特定の作品をいかに売るかというテクニックだしな。
要するに営業。