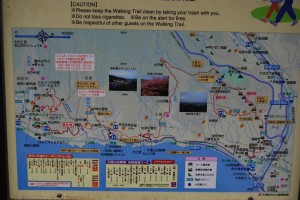j:com の smart tv boxちゃんが来たのでさっそくimagica bsで録画したブラックホークダウンやら、au video passで見放題の吉田類居酒屋放浪記などを見ている。book passでスマホにたくさんマンガを落としたから通勤途中に見るだろう。
それはそうと、[不良債権としての『文学』というのを読んだのだが、読んでみるとごく当たり前の主張だ。大塚英志氏の書いた本は、たぶん私が読むといらいらして読めないと思うのだが、要するに専門学校生や大学生にプロットの組み立て方を教える本であって、誰が書いても同じようなことは書くだろう。
戦前から戦後のある時期まで文学全集が馬鹿みたいに売れた時代がありました。その時の高収益体質は、細かく検証しませんが「文学」の既得権を形成した現在の高コスト体質に繋がっています。
文芸というものをビジネスモデルで見た、実に面白い指摘であり、たとえば永井荷風が大学教授を辞めて文筆業で食って行けたのはたしかに文学全集が売れたからであり、今日我々が「文豪」というイメージを抱いているのもそうした作家である。今や「紙」の文学全集や百科事典ほどばかげたものはない。ああいうものはようは、昔家を建てたときの家具や調度品の一種として買われていたものであり、神棚の一種で、別に実際に読んだりするものではない。本当に読もうという人には不便きわまりない。今ならウィキペディアやキンドルを読むだろう。多くの愛書家というのは結局は自宅に自分だけの文学全集を作ることが好きなだけであり、蒐集家の一種であり、だから紙の本が好きなのにすぎない。逆の言い方をすればキンドルではそういった蒐集癖を満足させることはできない。こどもが切手や昆虫やカードを蒐集するのが好きなようなものでこれはどうにもならない。
大塚氏はコストがかかりすぎる現在の出版業そのものを疑問視し、コミケを参考にした「文学フリマ」などというものを提唱しているが、これは今kdpの世界でまさに進行していることだろう。「文学」と同様、出版業界もまた既得権化しているからで、それは出版にコストとリスクがかかるからであり、よって元の取れる本ばかりが本屋に並ぶことになる。彼の言うことはいちいちもっともだと思う。
小谷野敦氏が「大塚の文章は非論理的で、下手というより平然と論理をすりかえる詭弁と直観だけで書いていて、それを実証的に検証しようという姿勢がない」と批判しているそうだが、確かにこの「不良債権としての『文学』」という一文を読むだけでも、そういう印象を受ける。威勢は良いが実がない気がする。
でまあプロットを作る技術を教えれば多くの人が小説を書けるようになるだろう。しかしこれはハリウッド的娯楽のプロットですとか、これはミステリー、これは恋愛のプロットで、起承転結があってここが盛り上がりで、ここで落とすとか、そういう文書技術の部分をどんどん取り除いていってあとに何も残らないのは、種のない果実のようなもので、それは天然自然のものではない。世の中は種なしブドウや種のないミカン、バナナ、無精卵のほうが好まれる。種があればそれをよけて食べる。パパイヤに種ごとかぶりつく人はいない。そんなゴリラかオランウータンみたいな食べ方はしない。
プロデューサーならば売れればそれで良いかも知れないが、原作者は実は自分の作品の中に種を仕込みたいのではないか。私なんかはそうだ。いや、作家になるのが最終目的であって何を書くのかというのはあまり関係ない、とにかく売れるものが書きたい、というのであればそれでもいい(逆に自己表現したい何かか自分の中に何もないと作家になれないから、わざと異常な体験をして特別な自分になろうとする人もいるわな)。「自己」より「人と人とのつながり」のほうが大事という人はいくらでもいる。どちらかといえば劇場でパフォーマンスしたい人や営業の人、プロデューサーなどがそうだ。
私は違う。私にとって文章というのは所詮は手段だ。私が死んだあとにもこの世に自分という種を残したい。種だけ残しても誰も見向きもしないから、そこにストーリーという果肉をまとう。みんな果実は好きだから食べる。種ごと食べる。せっせと食べてもらえるようなおいしい果実を作ろうと努力する。種ごとたべない人が多いかもしれないが、たくさん出回ることによって種の存在に気付いてくれる可能性は高まる。それが原作者のわがままだと思う。
トイストーリーやボルトなんか見ていると、原作者や原画のわがままなどという要素は注意深く、完全に取り除かれている。完全に種なしにされている。確かに繰り返し見ればみるほどにさすがディズニーだな、さすがハリウッドだなと感心されられるが、そこからディズニー的、ハリウッド的な要素を取り除くと何も残らない。完全に去勢されている。
ハリーポッターはさすがに原作がきっちりしているのと、原作も合わせて読むことができるから、原作者の鬱屈した自我というかどろどろとしたこだわりが伝わってくる。ハリウッドがそれをいかに子供にもわかるエンターテインメント作品に仕立てて、3DCGで飾っても、ある程度は残っていて、だからハリーポッターの作者は作品に種を残すのに成功しているといえる。
スピルバーグとルーカスを比べると、スピルバーグはユダヤ人、ルーカスはイングランド系だからかもしれんが、どちらもハリウッドの娯楽映画を作る人ではあるが、スピルバーグのほうがはるかに屈折したものを作り、ルーカスのほうがよりハリウッドに向いているといえる。私はどちらかと言えばスピルバーグのほうが好きだ。そういう苦さや雑味に味わいを感じるからだ。
スピルバーグやコッポラなんかの作品を除けばハリウッド映画は総じて予定調和であって、だいたい展開が読めるからつまらない。逆に老若男女だれでも安心して楽しめる。いくら激しいアクションがあっても箱庭の中で暴れているようなもの。いきなり主人公が死んだりしてパニックに陥ることがないようにできている。水戸黄門やさざえさんや笑っていいともがいつも同じなようなものだ。私なんかはよくまあああいうものを飽きずに見ていられるなと思うが。それだけ予定調和に需要があるからだろう。
そういう意味ではパーフェクトストームはほとんど唯一の例外で、私は最後に予想を裏切られてびっくりしたのだが、おそらく海の波を3DCGで表現することが至上命題で、そのため実話をなぞる必要があったのだろうと思う。そこには青の六号に対するハリウッドの激しい嫉妬・対抗心が感じられて面白いが、そういうところを楽しむことじたいハリウッド映画には想定されていない。
ま、そういう意味ではブラックホークダウンも若干ハリウッド的テンプレからは外れてるかな。でも今見るとやっぱりいたるところアメリカ臭がする。