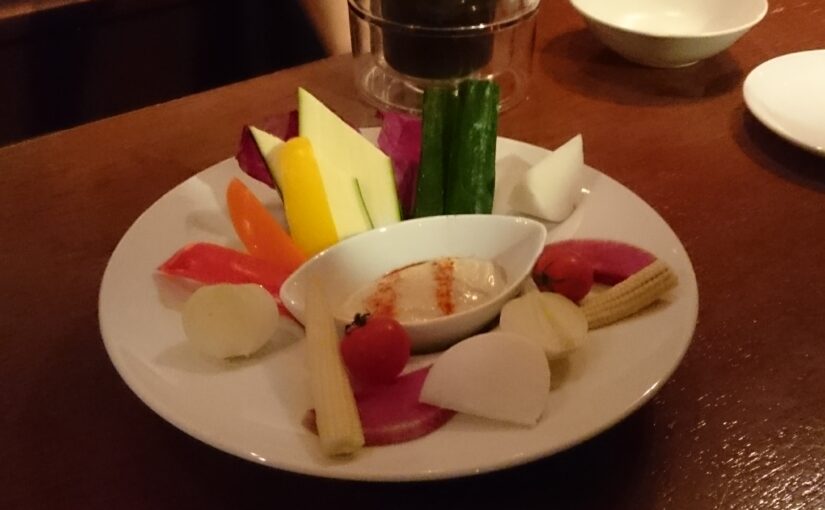知りたいのは、清朝末期の、科挙制度の改革、変法と科挙の関係、特に、康有為、梁啓超らの上奏文など。特に八股文の是非について。つまり、清朝末期の学制改革について。宮崎市定『科挙』も久しぶりに読んでみたが、これは、唐代から明清までの科挙の移り変わりについて、おおまかに書いてあるだけ。八股文については、「四書題」とあるのが、それに相当するか。その内容・形式には一切触れてない。まあ、あまり興味なっかたんだろうな。清朝については、『儒林外史』が少々、第三回辺りに出てくる、范進という万年浪人の話がおもしろおかしく引用してあるだけだ。『儒林外史』は清朝の前半、せいぜい雍正・乾隆帝の頃の話が反映しているだけで、清朝末期の光緒帝の頃のことがよくわからない。しかし、資料としては、光緒帝のころのものがもっとも豊富に残っているはずだが。
康有為、梁啓超らの論文だが、あちこちの図書館でも、断片的にしか手に入らない。ネットの情報も。彼らは、科挙や八股文が不要だと主張したのではなく、官吏や政治家を登用する制度が科挙に限られていること、近代的な学校制度がないこと、などを批判しているのだと思う。梁啓超の文章など読んでみると、科挙と平行して学校を作りましょうと言っているに過ぎない。北京大学の前身である京師大学堂が創設されたのは1898年というから、戊戌の政変で行われた改革の一つだったのだろう。この、戊戌政変から辛亥革命までの資料というのは、探せばいくらでもあるはずなのだが。
康有為の四番目の妻(妾)となった日本人、市岡鶴子というのを調べているのだが、詳しいことは何一つわからん。
中国名人為什麼願意迎娶日本女人? 2010年04月01日 来源:新華網
康有為晩年娶了日本少女市岡鶴子為小妾。1911年6月7日,康有為応梁啓超之邀,従新加坡移居日本,次年春,搬至須磨“奮豫園”,適妻子何旃理懐孕,儿女又年幼,便雇了16歳的神戸少女市岡鶴子作女傭。1913年康有為回国不久,市岡鶴子也来到了上海。在辛家花園的遊存廬,鶴子正式成了康有為的第四妾。1925初,28歳的鶴子懐了身孕,這年康有為68歳。秋,鶴子回日本生下一女,取名凌子。有人伝言康凌子并非康有為的骨肉。鶴子甚至但求一死以表清白。堅貞壮烈不下于蝴蝶夫人。
1911年6月7日に康有為は梁啓超に招かれてシンガポールから来日。牛込区早稲田、明夷閣。
1912年春、神戸の須磨の「奮豫園」に移り住み、16歳の少女、市岡鶴子を女中として雇う。
1898年に梁啓超は日本に亡命して横浜に住み、神戸と横浜を行き来していたが、1906年から神戸に住むようになっていた。1912年帰国。
康有為は1898年、香港経由で日本に亡命、1899年カナダで「保皇会」結成、以後、アメリカ、イギリス、シンガポール、インドなど、主にイギリスの植民地などを転々として、三回ほど来日したらしいが、詳しいことはもっと調べてみないとわからん。
1913年には市岡鶴子とともに上海へ。愚園路192号。辛家花園の遊存廬で正式に鶴子と結婚。鶴子17才、康有為55才。
1917年、復辟事件。
1923年、青島に定住。青島は、1914年に日本が占領してドイツから奪い、1922年に中国に返還し、特別行政区となった。中国領となった直後ということだな。
1925年秋、鶴子は日本に戻り、凌子を出産。鶴子29才、康有為67才。
1927年、康有為死去、69才。
1929年、梁啓超死去、56才。
魯迅『孔乙己』も、ごく短いものなので、さらっと読んでみた。