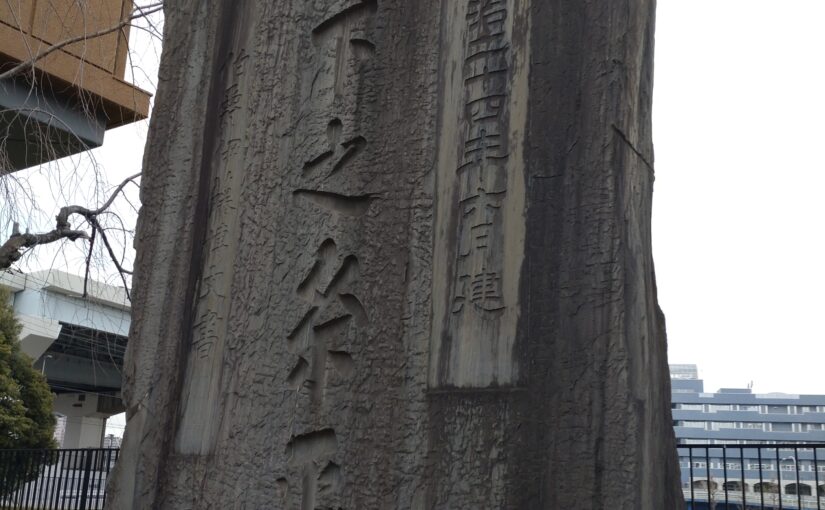今日のイブニングの『おせん』にいかにも小林秀雄風な「来宮秀雄」という人物が出てきて、「へぇへぇたしか高等部の国語の教科書で読まされたでやんす。なんか難しいっていうか、全然遊びも無駄もない文章で、まるで一切つなぎを使わねぇそば職人のような」「ほほうまさに言い得て妙」などというセリフがあるのだが。まあ確かになんというか、志賀直哉や芥川龍之介の短編小説などは「遊びも無駄もない」と言えるかもしれんが、小林秀雄の文章はときにかなり饒舌、冗長に感じる時があるのだが、気のせいだろうか。まれにただ単に原稿料を前借りしているだけではないか思われるときもあるのだが。
「一切つなぎを使わない蕎麦」が「全然遊びも無駄もない文章」に似ているかどうかも微妙だ。そういう文章は省略や余韻というものを多用している。つまり技巧として、本来あるべき語句をそぎ落としているのであり、和歌や俳句などの短い詩形などにもよく使われる。単につなぎを使わないだけではない。逆に短い詩形だからこそ、遊びを使うこともある。遊びを使うために省略もする。
ははあ。国語の教科書で小林秀雄というと「無常という事」なのか。読んだことないな。
「無常といふ事」だが、ごく短い文章なので、さらっと読んでみた。どうということもない文章だが、なぜこのように有名なのか。そしてやはりだらだらとした随想風だ。森鴎外が晩年考証家に堕したというのはとるに足らぬ説であり、同じことを宣長の「古事記伝」にも感じ、「解釈を拒絶して動じないものだけが美しい」「これが宣長の抱いた一番強い思想だ」などと書いている。難解な言い回しだがこれは単に「いろいろと想像で解釈をいじくり回すよりもたくさんの文献に当たって考証学的に意味を推量すべきだ」と言ってるに過ぎないのではないか。それと「常」と「無常」ということや、平安人と現代人の対比となっているのだが、やはり何が言いたいのかよくわからない。
果たして、「解釈を拒絶して動じないものだけが美しい」とは宣長の何を言っているのだろうか、と思うのだが、この「無常といふ事」は戦争中の昭和十七年に書かれたものであり、戦争中に読まれた「古事記伝」には特殊な意味があったに違いない。「本居宣長」は昭和四十年から書かれたものであって、当然昭和四十年に執筆を始めるときには宣長全集か何かを読み直した後のことであろう。だから、「無常といふ事」に書かれている宣長感は、後のものとはだいぶ違っているのに違いない。
ははあ。なるほど。これは、日本が戦争に負けてから出版されたので、「敗戦国民へ向けたメッセージ」として読まれたわけだ。そういう読み方もできなくもないが、それは明らかに誤読だろう。小林秀雄の宣長解釈もこの時点では何かあやふやであるし(そもそも小林秀雄の古事記伝解釈はちんぷんかんぷんだ)、それをまた読者は誤読しているわけだから、
小林秀雄の人気というのも実に怪しい。そしてそれを高校の国語の教科書に載せて、いったい何を読解しろというのだろうか。不思議だ。
追記。「解釈を拒絶して動じないものだけが美しい」とはつまり、古事記に書かれている神話というものは解釈不能なもので、信じるとか信じないとか嘘とかほんとうとか今の時代の価値観とは切り離して、古代人が感じたままに鑑賞すべきであって、だからこそ美しい、と言いたいのだろう。あらためて「無常といふ事」を読み直してみたが、どうしようもない駄文だ。この文に何か意味があったとしてそれを理解することにどれほどの価値があろうか。
「過去から未来に向かって飴のように伸びた時間という蒼ざめた思想」とか「現代人には、鎌倉時代の何処かのなま女房ほどにも、無常という事がわかっていない。常なるものを見失ったからである」など、気取って、言葉をもてあそんでいるだけにしか見えない。