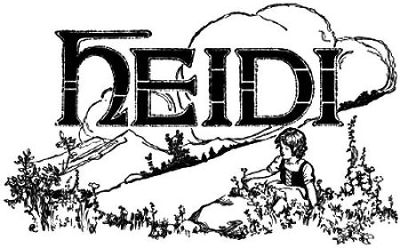Hier wohnte der Geißenpeter, der elfjährige Bube, der jeden Morgen unten im Dörfli die Geißen holte, um sie hoch auf die Alm hinaufzutreiben, um sie da die kurzen kräftigen Kräuter fressen zu lassen bis zum Abend; dann sprang der Peter mit den leichtfüßigen Tierchen wieder herunter, tat, im Dörfli angekommen, einen schrillen Pfiff durch die Finger, und jeder Besitzer holte seine Geiß auf dem Platz. Meistens kamen kleine Buben und Mädchen, denn die friedlichen Geißen waren nicht zu fürchten, und das war denn den ganzen Sommer durch die einzige Zeit am Tage, da der Peter mit seinesgleichen verkehrte; sonst lebte er nur mit den Geißen. Er hatte zwar daheim seine Mutter und die blinde Großmutter; aber da er immer am Morgen sehr früh fortmusste und am Abend vom Dörfli spät heimkam, weil er sich da noch so lange als möglich mit den Kindern unterhalten musste, so verbrachte er daheim nur gerade so viel Zeit, um am Morgen seine Milch und Brot und am Abend ebendasselbe hinunterzuschlucken und dann sich aufs Ohr zu legen und zu schlafen. Sein Vater, der auch schon der Geißenpeter genannt worden war, weil er in früheren Jahren in demselben Berufe gestanden hatte, war vor einigen Jahren beim Holzfällen verunglückt. Seine Mutter, die zwar Brigitte hieß, wurde von jedermann um des Zusammenhangs willen die Geißenpeterin genannt, und die blinde Großmutter kannten weit und breit Alt und Jung nur unter dem Namen Großmutter.
この小屋に山羊飼いのペーターという男の子が住んでいた。彼は12才で、毎朝デルフリの山羊を集めて、それらをアルムの上まで連れて行き、短い野草を食べさせて、夕方まで放し飼いにする。それから、指笛を吹きながら、身軽な家畜たちをデルフリまで下ろしてきて、それぞれの山羊の持ち主は広場まで受け取りにくる。多くの場合は男の子や女の子が受け取りにくる。というのは、ひとなつこい山羊たちはめったに暴れないし、またペーターが自分の同輩らと夏の間に会えるのはその時しかなく、それ以外の時間は山羊とばかり一緒に暮らしていた。むろん彼には家に彼の母と目の見えない祖母がいた。しかし彼はいつも朝とても早く家を出なくてはならなかったし、できるだけ長い間友人たちとおしゃべりをして過ごしたかったから、夕方遅くデルフリから家に帰ってきた。彼は家に居る時間をできるだけ短くして、朝と夕方、パンとミルクをあっという間に飲み込むように食べてすぐにベッドに横になって寝てしまった。彼の父は以前彼同様の仕事をしていて同じくペーターという名だったので、彼と同じく山羊飼いのペーターと呼ばれていた。しかし彼は数年前に、山で木が倒れてくる事故で亡くなった。彼の母は、ほんとうはブリギッテという名だが、みんなから「山羊飼いのおかみさん」と呼ばれていた。そして目のみえないおばあさんは年寄りからも若者からもみんなただ「おばあさん」と呼ばれていた。
sich aufs Ohr zu legen 直訳すれば、耳の上に自分を横たえた。